�@�@�@ �@�@�@�@�@�@
�ځ@�@��
�y���W�z�e�x���́u�t�̌𗬉�v�̕� |
�@ |
�e�x�� |
1 |
���N�̑��̕� |
���R�x�� |
��g �Ԏq |
�@
6 |
�ɂ��܂��فA
�@�@�@�@�u���R�s����فv�̃X�P�b�` |
�����x�� |
���c �F�I |
7 |
�u�q�ǂ����v�̑̌�����u�q�ǂ���
�@�@�@�@�L���Ȏq�ǂ�������v�i��ҁj |
�����x�� |
�c�� �@�� |
7 |
�A���@�o��ƃX�P�b�`�̗�
�@�@�@�@�@�@�j���[�W�[�����h��(�P) |
�����x�� |
���� ���Y |
11 |
�܂���l ��Ȓ��Ԃ��V���֗��������i��ҁj
�` �Ɩ�E�n��E�א�E�����搶�� �` |
�����x�� |
�ݖ{ ���Y |
13 |
�����邱�Ƃ́@����悵�@����
�\�\���t�@����b���q�搶���Âԁ\�\ |
���R�x�� |
���� �͎q |
15 |
��Q��V���R���j�T�K(�ʎZ52��)�̂��U�� |
�����x�� |
���@�@ �� |
17 |
�ҏW��L
�@ |
�@ |
�ҏW��
�@ |
19
�@ |
�@
�@
�@
�@
�u����x���@�t�̌𗬉�v ���� ���炵�����N�����v���U
����x���@���� �ې�
�@

�@�R��23��(�y)�A���̓��͒����珬�J�A�ԗ₦�A���̉ԉ�͂܂������B���́A���炵�����N�����v���U102���C���A12��30���J�n�A�Q���҂V���B�R���i�ЂŒ��~�̂R�N�Ԃ�����ŁA17��(2015�N�R��)�����N��22��܂ŁA�U��ɓn���āA���H�E�~�j�u���E�𗬂Ƃ����`�Ŏ��{���Ă����B�����23��͒��H�E�𗬂݂̂̊J�Âł���B
�@��N���p���Ă����{�ݓ��̂��X(�z�b�g�^�C��)���R�����ŕX�A�R���ɓ����Ă��ٓ��̗\��̔��͒��~�Ƃ������ƂŁA�}篁A�O�D��́u�A�i�S�сv�𒍕�

�����B���l�i��1,580�~�A�Q���҂����Ȃ��A�\�Z�ɗ]�T���������̂ŁA580�~�̕⏕���\�ɂȂ����B�����́A���҂��Ă������A������ł��Ȃ������B�����A���߂ĐH�ׂ�悩�����̂�������Ȃ��B�H�����ς�Ō𗬂̎��ԁA���݂��̋ߋ�����荇�����B���̂ق�̈ꕔ������Ă݂悤�B
�@�u��������Ƃ����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ����A���₩��ƖZ�������Ă���B�v�u�n��̘V�l����̂U���ʼn��U���邱�ƂɂȂ����B(���b���̌�p�҂��₦��)�v�u18���L�����s�̈��ԃG���O�����h�����Ƀ_�E���A�d�C�����Ԃ̓��Y���[�t���U�J���҂��ŃQ�b�g�����v�u�䂪�Ƃ̔��ɁA���ɃC�m�V�V�����K�A��Â���s���`�v�u�Ȃ��A�I���E�I���E�I���Ɛӂߗ��Ă�v�u�ƂɂȂ��Ă����䂪�Ƃ̕ꉮ�̂Q�K�ɁA���Ƒ��������z���Ă���B�Еt����Z���v�u���f�d�b�h�~�@�\�t���d�b�@���w���B�i�s�̕⏕��7,000�~�ɖڂ�����j�v
�@�𗬌�A���N�x�ȍ~�̂��̉�݂̍���ɂ��Ĉӌ������������B�ꏊ�A���e�A

���{�����ɂ��Ęb���������B�Ƃ肠�������N�x�́A�u�����̒n�v�ł���Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B�u���@�v�u�W�[���Y�X�g���[�g�v�������ɕ����B
�@�R�������O�ɕ�A���y�Y�̂��َq�l�����ƈ��ݕ�����ɋA�H�ɂ����B���N�͎����ʼn�܂��傤�B
�@
�@
�����x���@�t�̌𗬉��
�����x���@���� �e�`
�@
�@�R��23���y�j���A11���̎Q���҂������x���t�̌𗬉�́A���j�ƕ����̑��������������ƂȂ�܂����B
�@�ŏ��̌��w�n�ł���ՏƎ����́A�ՏƎ��{�̂��}���w�O�̋�搮���ɔ����Ĉړ]����Ă������̂́A���ꂾ���͋��}���̒��S�n�Ɏc��A400�N���������ւ鋐��Ȏ}����C�`���E�̖Ƌ��ɁA�[�����j�̏d�݂�����������
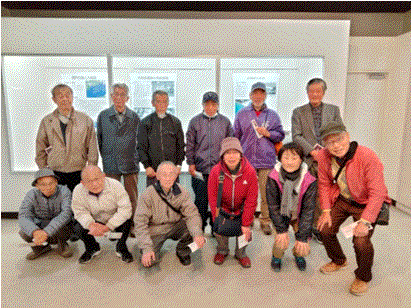
�������̂ł����B
�@�����ĖK�ꂽ���@�́A�Ԃ����O�傪��ۓI�Ȏ��@�ŁA���������24���ɂ́u��傳��v�ƌĂ�鉏�����J�Â���A�����̘I�X�ƎQ�w�҂œ��킢�܂����A����̖K��ł͐Î�ɕ�܂�钆�A���̒��ق��t�Ɉ�ې[�����̂ƂȂ�܂����B
�@���y�قł́A�y�j���ɂ�������炸�J�ق��ĉ�����A�s�̊w�|���̕��ɂ�钚�J�ȉ���܂Ŏ邱�Ƃ��ł��܂����B���Ɉ�ۓI�������̂́A�u��v�Ƃ������O�́A�{���ɏ����ȓ�����o�y�����A�ڂ�������悤�ȏo�y�i�̐��X�ł����B�����g���q�C�̈��S���F���ė���������Ƃ���邱�̓��́A���̗��j�I���l�����߂ĔF������������̂ƂȂ�܂����B
�@���ɁA�}���s�̂Q��L�˂ł���A�É_�L�˂ƌ��̊L�˂ɂ��Ẳ����

�܂����B
�@�É_�L�˂���o�y�����l���̒��ɁA���E�ŌÁi3000�N�O�j�̃T���̋]���҂ƂȂ����l�������������Ƃ��A���������ߔN�̌����Ŕ����������Ƃ�A�ʉߋV��Ƃ��Ă̔��������������ƁA�����̊C�ݐ��ƌ��݂̊C�ݐ��̈Ⴂ�Ȃǂɂ��Ċw�т܂����B
�@����A���̊L�˂́A�É_�L�˂�肳��ɌÂ��N��̂��̂ƕ�����܂����B�吳����̋��s��w�̒����ł͌�����Ȃ������l�����A�ۈ牀�g���H���Ŕ�������A���̍ۂ̎ʐ^�Ɏ��i�����e�`�j�̉Ƃ��ʂ��Ă��āA���ݕۈ牀�̌����Ă���Ƃ��낪���̊L�˂��������Ƃ�A���̓y�n���q������ɂ͉䂪�Ƃ̈␅�c�ƔF�����Ă������ƂȂǂ��A�Ȃ������v���o����܂����B
�@�Ō�ɖK�ꂽ�̂́A���˓��C�̐V�N�ȊC�N�������y���߂�u��悵�v�ł����B�h�g�A�ϋ��A�V�Ղ�ȂǁA�n���̏{�̐H�ނ��g�����������Q���҂�����܂����B
�@�H�������Ȃ���A�Q���҈�l��l�̃��j�[�N�ȋߋ����s���A���������Ȃ���A�a�₩�ŗL�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B
�@���̌𗬉�A���N���Q�����悤�Ƃ����@�^�����߂Ă��ꂽ���̂ƐM���ċ^���܂���B
�@���x���̊F����A���N�͊}���ɗ���ׂ��ł��B�u��悵�v�̗��������ł��A��x������Ă݂鉿�l�͏\���ł���I
�@
�@
����x���@�t�̌𗬉�
����x���@���W �M�V
�@
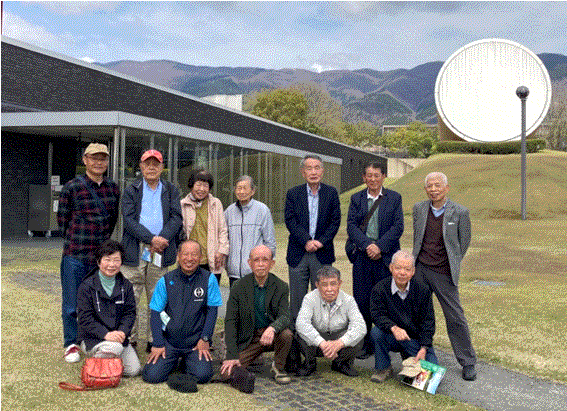 �@�S��11��(��)12���̎Q���ɂ�����x���w�K�𗬏W����J�Â��܂����B�ߑO���A�ދ`��������p�ق����w�B�w�|���̐����̂��ƁA�X�ɂP���Ԃ��܂�B75�ˈȏ�͖����B���Ȑ\���B75�˖�����700�~�B�قƂ�ǂ̎Q���҂������فB�ߌ�ׂ͗̃��X�g�����ʼn�H�ƌ𗬁B�s�b�c�@�ƃp�X�^�̟������X�B���N�̍ĉ�������ĕ�܂����B
�@�S��11��(��)12���̎Q���ɂ�����x���w�K�𗬏W����J�Â��܂����B�ߑO���A�ދ`��������p�ق����w�B�w�|���̐����̂��ƁA�X�ɂP���Ԃ��܂�B75�ˈȏ�͖����B���Ȑ\���B75�˖�����700�~�B�قƂ�ǂ̎Q���҂������فB�ߌ�ׂ͗̃��X�g�����ʼn�H�ƌ𗬁B�s�b�c�@�ƃp�X�^�̟������X�B���N�̍ĉ�������ĕ�܂����B
�@
�@
���R�z���u��|�h�v�Ɓu�����V����v
���k�x���@�y��@��
�@
�@����̔��k�x���𗬉�͎v�Ă̖��A��|�E�䌴�ɉz�������B�V��s���ō��̊J�Ԃ��x��Ă���R��30��(�y)�X���A���Љw���R�{�A�팩�A�����搶�Ɠy��͎Ԉ��ŏo�������B�v��o�R�ŋg���^��������ڎw���Ԓ��A�������^���Ɩ�|
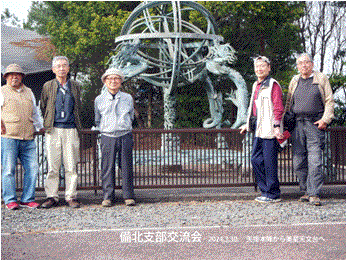
�̓��ɂ��邱�Ƃ�m��B�Ƃ�����\��ʂ��|�̋g���^�������ɓ������A���{�搶�ƍ����B�Q���҂T���ōL�������́u�g���^�����v���Q�q�����B�\�莞�Ԃ��������߂������A�Ԃ͖�|�h�Ɍ�����10��20���ɓ����B�����ɋ��{�w�u�Έ�Ɓv�Ɍ��������B
�@�����ł̓��b�L�[�����A�܂����ꗿ���i�`�e�J�[�h�̂������Œc�̈����ɂȂ�A�K�C�h�{�����e�B�A�̈ɒB����ɂ����b�ɂȂ����B
�@���@����̕ꉮ�͐����喼��V���@�ĕP���������u�䐬��v�A�x����Q���܂�����������ȂǍ��̏d�v���������ɒB����͔����̏�Ƀ��[���A�����Ղ�K�C�h�����ĉ�����ꓯ�y���B�㔼�̎𑠂͓�g�̌��w�q��������Ă����₩�ɂȂ����B���H�́A�h�꒬�̖ʉe�𗯂߂��{�w�ʂ�����������A�\��̌Ö��Ɓu�V�[�Y�����Ɓv�ł������H����ۂ芽�k�����B
�@�������ł́u������s�v���o�ĉ����ʼn������̂��V�C�̒��A�V����������B
�@13��45���A�J�قƓ����ɓ��فB�܂��R�c���K�l���|���ė��̉f���ɂ��F���̗���30���ӏ܁B���̌�A101��^�]������^�߂ɐE���̉�������B���̓V����ƈ���đ��ړI�g�p���\�œ��Ɉ����Ő���o�����ƌւ炵���ɐ������ꂽ�B�V��h�[���̊J�A����Ȗ]�����̐���E�쓮�A���ʂ̏��~�ȂǂɊF�A�����I�����I�����B���̌�e���X�ɏo�A�~�n���ɗ���覐Ίϑ��A�F���S�~�ϑ��A���z�ϑ����̓V����{�݂��m�F�����B�c�O�������̂́A�����Ɖ_�̂��ߐ��̊ϑ����o���Ȃ��������Ƃł���B
�@�{�ݑO�ɂ���ӓV�V�i�����A����̓V�̊ϑ����u�j���v���J�O�ŏW���ʐ^���B���ċA�H�ɂ����B����͑z��O�̊w�K�Ńn�[�h�ɂȂ������[����������ƂȂ����B
�@
�@
���R�x���E�����x���̏t�̌𗬉�
���R�x���@���Á@�W
�@

�@�S��16���i�j�A���R�x���E�����x�������̏t�̌𗬉�������Ȃ��܂����B
�@����͍D�]�������O��̌�y���ɂÂ��A���R��E�G��������߂���U��ƁA���ł��傫�Ȗ��Ƃ�����p���X�`�i���̍u���Ƃ������e�ŁA�Q���\��29���̑S���Q���āA�D�V�̂��Ƒ傢�Ɋw�K�ƌ𗬂�[�߂܂����B

�@�S���ł̏W���ʐ^�B�e�̂̂��A10�����x�̂R�̃O���[�v�ɕ�����āA�a�c�ΐ搶���͂��߂Ƃ���{�����e�B�A�K�C�h�R���̕��X�ɐ擱���������A��ɑ�K�͂ȐΊ_�̊O���������ƎU�ĉ��܂����B����܂ʼn�������܂�m��Ȃ������z��̗��j�Ɏ����X���A�����H�@�ɂ���ĕς��Ί_�̎p�ɖڂ�������A�ǂ̉��������喞���̊��z��������܂�

��
�@���̌�A�����}���قQ�K�̃T�[�N���������Ɉړ��A���ԓ��ٓ��i���R�썂�Z�̐��k�Ƃ̃R���{�ٓ��j�̒��H�̂̂��A�Q���҂̋ߋ��Ō𗬂��܂����B
�@�ߌ�̍u���ł́A���y�̓����G���搶����u�p���X�`�i���ɂ��āv�Ƒ肵�Ė�P���Ԃ��b����
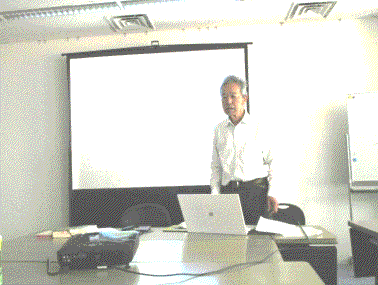
���������܂����B���������m���Ă���悤�Œm��Ȃ��p���X�`�i���B�Η��̍����Ƃ����A���_�����E�L���X�g���E�C�X���������ꂼ��̌n���A�����p���X�`�i���̗��j�i�L���X�g�����͂ɂ�郆�_�������Q�A�ߑテ�_���l�̌o�ϗ́A��ꎟ����̃A���u�̓Ɨ��E���_�����k�̃V�I�j�Y���^���A���풆�̃i�`�X�̃��_���l��Ő���A�����̍��A�ɂ��p���X�`�i�����āA�C�X���G���̗̓y�g��A�K�U�n��̊�@�Ȃǁj�ɂ��Ă�������b���Ă��������܂����B�����ɂ��������n��҂̐��ɂ�������悤�ɁA�o���̑Η��ӎ��͋~���������Ƃ��v���܂����A���Ԃ�ŊJ����ɂ͍��ې��_��傫�����߂Ă������Ƃ��K�v�ł���A�o���ƑΓ��ɘb�̂ł���͂��̓��{�̖������d�v�ł͂Ȃ����Ƃ̎w�E����ۓI�ł����B
�@�Ō�ɗ��N�x�����N�ȏ�Ɍ𗬉��グ�悤�Ƃ��݂��ɐ����A����
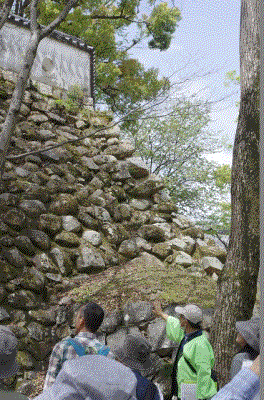
�܂����B�ȉ��Ɏ�Ȋ��z���Љ�܂��B
�@
�y �𗬉���I���Ă̎Q���҂̊��z �z

�����R��̃K�C�h�t�����w�͂ƂĂ��y���߂܂����B�Ί_�̈Ⴂ�@����������y���ނ��@�Ƃ��ł��܂����B�߁@��̓����搶�̍u�`�@�����ɂȂ�܂����B�@��悳�ꂽ���X�A���肪�Ƃ��������܂����B�i���@�L�O����j
�����܂Œm��Ȃ������G������̂��ƁA�ڂ��������Ă����������ɂ��Ȃ�܂������A�Ί_��傫�Ȏ�����Ɏc����Ă���y���������ł��B���F�Ƃ��b���܂����B�܂��u���ł́A���̕����̌��ƂȂ���j�A�����̂��Ƃ��m��Ă悩�����ł��B��͂���j����w�ԕK�v������܂��ˁB�i�R�����q����j
����N�Q�����������v�����̂ł����A�n���i�����}���ق���k��15�����x�j

�Ȃ̂ɁA�����m�炸�ɐ����Ă����ƒɊ��B�Ί_�������N���i��C�������āj�c����Ă���I�Z�ؐς݂��ǂ̂悤�ɍl���Ċ��������Ă������̂��B����������������ł����B�i������Î}����j
���V�̔������G������A�V�C���ǂ��A�C�����̂����ꎞ�ł����B�G�邪�u�Ί_�̏�v�Ƃ����̂����Ȃ����܂����B�ߌ�̍u���A�p���X�`�i���ɒ����@���Η�������

���Ƃ͂킩��܂������A��������ł����B���ې��_�Ő����������ɂȂ邱�Ƃ��c�B�i���c�G�b����j
�������搶�̍u�����āA���_�����A�L���X�g���A�C�X�������̗��j�Ƒ�ꎟ���E���̂Ƃ��́u�C�M���X�̎O����O���v���傫�����܂��Ă��邱�Ƃ����߂Ēm�邱�Ƃ��ł����B�p���X�`�i�Ƀ��_���n�ƃA���u�n�̂Q���Ƃ����݂����悤���ې��_�Ō��߂邵���Ȃ��Ǝv�����B�i�ݖ{���Y����j
�@
�@
���N�̑��̕�
���R�x���@��g �Ԏq
�@�S���V��10�����牪�k�w���ŁA�N�Ɉ�x�����̌��N�̑��������J���܂����B���̒�̍����炫�ւ��ď����B���V��ł��܂����B�V�����\��l�߂�ꂽ�l�H�ł̃O���[���Ƀs���N�F�̉Ԃт炪�����ƁA�i����??�Ԃ��̂܂܂��Y��Ȏp�ő�R�����Ă���̂ł��B�����Ԃ̂�������Ŗ����z���Ă͎̂ĂĂ����̂ł��B

�@��K�̃t���A�͍L���ė����ɂ��D�����Y��ɐ����āA���z�̌��𗁂тĂ��܂����B��A�������͌������x�݂ŁA��㎁�A�Έ䂳��A��炳��A�ߊ}����A��g�Ɛ^���@�̑���̓����ł����B
�@�܂��A�k�����H�̢�\����Ŕ������K�A��̎w�⏶���h�����ċC��������Ƃ��납��A���A���w�A�r�A���ȂǂƑS�g�̊߂�ؓ��������C�����ǂ��ʓ���������A���K�̂��Ȃ���l��������܂����B
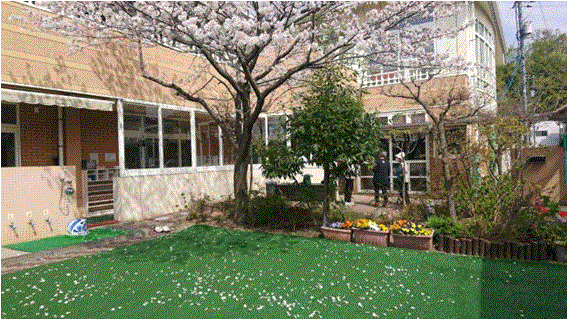
�@�F����͂���]���Ɏg�����݂�����Ă���ꂽ�̂ŁA���b���������ł����ɂȂ�܂����B���퐶���̒��ő�������̑���s���̗ǂ���ʂōs���ĖႤ�Ƃ������Ƃʼn��U���܂����I
�@���N�̑��N�ۈ牀����Ă��Ă��܂������A�C������������ɎQ���҂����������̂Œ��~�����ė~�����Ǝv���܂����B
�ɂ��܂��فA�u���R�s����فv�̃X�P�b�`
�����x���@���c �F�I
�@2024�N�R��31���������āA���R�s�̏鉺�ɂ��鉪�R�s����ق͕قƂȂ�܂��B1963�N�ɏv�H����A�������v���̐v�ɂ�邻�̃��_���ȃf�U�C���́u���{�ɂ����郂�_�����[�u�����g�̌��z�v(DOCOMOMO.japan�j�ɂ�������ꂽ���̂ł���Ƃ��B���̉�ق̕ǖʂ͂��߂ɂȂ��Ă�悤�Ɍ����܂����A���͐����ŁA�����̊Ԃɓ����Ă���X���b�g�ɂ���Ď߂ɍ��o�����̂������ł����A������ʔ����Ƃ���ł��ˁB
�@���R�s����قł͗l�X�ȃA�[�e�B�X�g�̌����A�����A���̑��C�x���g�Ȃǂ��s���A���̉�قł̂��낢��Ȍ����Ȃǂ��y����ŁA�����Ă��낢��Ȏv���o�������Ă�������������Ǝv���܂��B�����Љ�l�ƂȂ��āA�{�i�I�ȉ������ŏ��Ɍ����̂͂��̉��R�s����قł����i�����́u�s������A���݂́u����
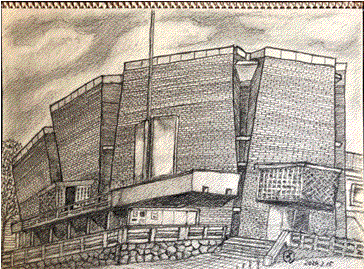
�ӏ܉�v�ɂ�)�B�܂��A���R�����g�̎��g�݂ŁA1981�N�Q��22���ɁA��P��u���k�ƕ���Ƌ��E���ł��镶���ՓT�v(1400�l�Q���j�����̉�ق�����Ă�����v���o������܂��B�������͍����g�̎��s�ψ��ł������A���L���̒|���ǗY���̔M�ӂő�K�͂Ȃ��̉���������ƋL�����Ă��܂��B
�@2023�N�Ɂu�n���m���v�Ƃ����V���Ȍ���A���M�̏ꂪ���ꂽ���ƂŁA���̖����͏I�������̂ł����A��y���̑Ί݂Ɉʒu���A���R��̐��ɂ��邱�̈�p�͉��R�s���̌e���̏�ł���ƂƂ��ɁA�O�荂���|�p�╶���̔��M�̒n�ł��������Ƃ͋L������Ă��ėǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̎v���o���������g���݂��߁A�܂������̕��ƃV�F�A�������ŃX�P�b�`�����Ă��܂����B
�@
�@
�u�q�ǂ����v�̑̌�����u�q�ǂ��ɖL���Ȏq�ǂ�������v�i��ҁj
�����x���@�c���@��
�@
�P�D���Z���ɖ��B����̈��g�̌��������
�@23�ō��Z���t�ƂȂ�A�s���V�����ƍ��Z�E���Ѝ��Z�A���˓썂�Z�ŋ��ڂ����܂����B�V�w���A�ŏ��̎��ԂɕK�����ȏЉ�ō��ɓ��A�W�A�̒n�}��`���A�u���g�̌��v�����܂����B���Ѝ��Z�ł́u�c���搶�͒����l���v�Ƃ������킳���L����܂����B
�@�푈�ōł��]���ɂȂ�͎̂q�ǂ��E�����ł��邱�ƁA�����̎q�ǂ��E�������嗤�i�����j�┼���i���N�j�̓y�ƂȂ������ƂȂǂ�b���܂����B���ɁA����Ńp���������˂āA�]�R�Ō�w�Ɏ��ӂ��ꂽ�̌��̘b�́A���k��������l�ɂȂ����Ƃ��A�y����͓����ڂ̍����ŁA�P���A�����͌����Ă��Ȃ��z���v���o���Ăق����Ɗ�������߂Ęb���܂����B80���ĂȂ����g�̌���N���Ɋo���Ă���̂́A���Z�Ő��k�����ɑ̌��k����葱�������߂��Ǝv���܂��B
�Q�D�S�Ă̎q�ǂ��ɖL���Ȏq�ǂ������
�i�P�j�u�q�ǂ����v�̑̌��͐l���݂̂������
�@��q�����悤�ɁA���͋Q����u�l�̐��Ǝ��v��g�߂Ɋ����A�s���Ƌ��|�ɂ��т�����X������܂������A�����]�R�Ō�w�A�w�Z�̐搶���Ȃǎ��͂̉������܂Ȃ����Ɏx�����Ďq�ǂ������߂����܂����B���l���āA�u���a�v�u�l���v�u���ʁv�u����v�Ȃǂ𐄍l����Ƃ��A���B����̈��g�̌��͎��́u�݂�����ׁv�ɂȂ��Ă��܂��B������݂āA���܁A�q�ǂ������͕��a�̂����ɁA���ʂŁA�L���ȑ̌������Ă���ł��傤���B
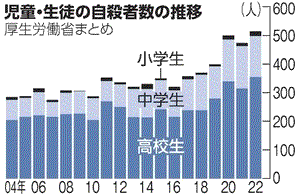 �i�Q�j���{�̎q�ǂ��̎���
�i�Q�j���{�̎q�ǂ��̎���
�@���{�̎q�ǂ��̕n�����͐[���ł��B2023�N�̎q�ǂ��̕n������11.5���ŁA8.7�l�ɂP�l�A207.6���l���n���ɚb���ł��܂��B�܂��A10�N�Ԃ�2.6�{�i2022�N�x�F29.9���l�j�ɂȂ����s�o�Z���A�N��20�����������s�ґ��k�����A18�N�ԂŖ�Q�{�ɂȂ������������̎��E���i2022�N��514�l�j�A�����߂⒆�r�ފw�ȂǁA�q�ǂ������X�����Â炭�A�X�g���X�ŐS�ɏ����Ă��āA�u���S���āA���M�������āA���R�Ɂv�����Ă���Ƃ͌����܂���B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�i�R�j�q�ǂ��̋�����������A�u�q�ǂ��̌����v�ۏႷ��u�q�ǂ��̌������v
�@�������ɂ��Ă��邱��
�@�@�@----�q�ǂ��́u�őP�̗��v�v�E�q�ǂ��́u�����̎�́v----
�@�@���̏��̓����́A�q�ǂ����u�ی�̑Ώہv�ł͂Ȃ��A�u�����̎�́v�Ɓ@ ���ĔF�߂��Ă��邱�Ƃł��B��l������Ɂu�q�ǂ��ɂ������Ɓv�����߂@���A������������邱�Ƃ͂ł��܂���B��l�́A�u�����̎�́v�ł���q�@ �ǂ��Ƃ̊ԂŁA���̎q�ǂ��̔��B�i�K�ɉ������R�~���j�P�[�V������}��A�@�����̈ӎv�a�ʂ�ӌ������̒�����A�u�őP�̗��v�v���������Ă����˂@ �Ȃ�܂���B
�A�������̑傫�ȓ����u�ӌ��\�����v�i�u�ӌ�����錠���v�j
�@�@���́A�q�ǂ��Ɂu�ӌ��\�����v��ۏႵ�܂����i12���j�B����͎q�ǂ��@ �����Ɏ����ɊW����S�Ă̎����ɂ��āA��l�ɑ��Ĉӌ����q�ׁA���́@�ӌ�����l�ɂ���ď\���ɒ�����錠����F�߂����̂ł��B��l�́A�q�ǂ��@�����̋C������ӌ������݂��A���̈ӌ��ɐ����ɉ������Ȃ���Ȃ�@�܂���B���������q�ǂ��Ƒ�l�̂��Ƃ�̒��ŁA�q�ǂ��ɂƂ��Ắu�őP�@�̗��v�v������������A�����āA�q�ǂ����ЂƂ̐l�i�Ƃ��Đ������B���ā@�����̂ł��B
�B�q�ǂ��̐������B�ɂƂ��ĕK�v�Ȃ���
�@�@���́A�q�ǂ��̐������B�ɂƂ��ĉƒ�����ʂ�����Ȗ�����F�߂ā@���܂��B�q�ǂ��̗{��ɂ��Ă̐e�̐ӔC��F�߁A���̐ӔC���ʂ������߂́@���̉������߂Ă��܂��i18���j�B�q�ǂ����������s�g����Ƃ��ɁA�e�͓K�@ �Ȏw���Ǝw�����s���A���͂��̐ӔC�ƌ����d���邱�Ƃ����߂Ă��܂� �i�T���j�B
�i�S�j�u���ǂ���{�@�v�E�u���ǂ��ƒ뒡�ݒu�@�v�i2023�N�S���{�s�j�A
�@�@ �u���ǂ���j�v�i2023�N12���t�c����j������
�@�u���ǂ���{�@�v�͏��́u�S�̌����i���ʂ̋֎~�A�q�ǂ��̍őP�̗��v�A�����E�������B�Ɋւ��錠���A�ӌ���\�����錠���j�v��@�������A�u���ǂ��ƒ뒡�ݒu�@�v�͎q�ǂ��ɑ���{��ɂ����āu�q�ǂ��̈ӌ��d���A���̍őP�̗��v��D�悵�čl�����邱�Ƃ���{�Ƃ���v�Ƃ���܂��B�����̂��Ƃ����邱�Ƃ��A�^�Ɏq�ǂ���������̂Ƃ��āu�q�ǂ��̌����v��ۏႷ�邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�u���ǂ���{�@�v�͎����̂��u���ǂ��{��v�𑍍��I�ɍ��肵�A���{���邱�Ƃ��Ӗ��ł���Ƃ��Ă��܂��B�i��T���E��10���j����ɂ���āA�����̂̎q�ǂ��v��i�q�ǂ��̌�����i�삵�A����𑣐i���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ����v��j�Ƃ��āA�u�q�ǂ��̌������v�Â����i�߂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�q�ǂ���ی�҂Ȃǂ̈ӌ��f�������{��̎��s���\�i��11���j�ɂȂ�܂����B
�i�T�j�u�q�ǂ��̌����v���x����u�ӌ��\�����v�Ɓu�q�ǂ��R�~�b�V���i�[�v
�@�q�ǂ��̈ӌ�������
�@�@�����q�ǂ��ɂƂ��čőP�Ȃ̂��́u�q���̈ӌ����v������ő�����d�@���邱�Ƃ���ł��B�u�q�ǂ��̍őP�̗��v�v�͉����f����ɂ͑�l�́@ �x�����K�v�ł��B�������A�q�ǂ��̋����E�S�E���v�Ɋ������ǂ������u�q�@���̈ӌ����āv���f���Ȃ���Ȃ�܂���B
�A�q�ǂ��̌������̊j�Ƃ��Ắu�ӌ��\�����v
�@�@�ӌ��\�����͎q�ǂ��̌������̊j�ł���A���������邽�߂ɂ́u�q�@�ǂ��̌����i��@�ցi�q�ǂ��R�~�b�V���i�[�E�q�ǂ��I���u�Y�}���j�v��݁@ �u���邱�Ƃ��K�v�ł��B����͑�l�̗͂Ȃ��ł͎����ł��܂���B���������@�āA�^�Ɏq�ǂ��̌�����ۏႷ�邽�߂ɂ́A�u�ӌ��\�����v�̊����ɂ����@ ���Ɂw�q�ǂ��̈ӌ��\�������u�\�ɂ�����v����A���A�����Ɓ@��Ȃǂ�����炿�̏�ʂŁA�q�ǂ��ɂƂ��āu�Ӌ`������v�A�q�ǂ��́u�́@��L���悤�ȁv�Q����ϋɓI�ɑ��i���邱�Ɓx����̉����邱�Ƃł��B
�B�u�q�ǂ��R�~�b�V���i�[�v�̕K�v��
�@�@���݂̓��{�Ɂu�q�ǂ��R�~�b�V���i�[�v���K�v�Ƃ����ő�̗��R�́A�q�@�ǂ����߂�������[�������Ă���ɂ��邱�Ƃł��B�q�ǂ��Ɋւ��Ė�@�肪���������ۂɁA�u�q�ǂ��̌����v�̎��_�ɗ������A��l�̎��_���D�悳�@���P�[�X�����������܂��B�܂��A���s�s�ȍZ���i������u���b�N�Z���j�@��ς��悤�Ǝ������k�������グ�Ă��\���ɑ��d���ꂸ�ɁA���̌㐺���グ�@�邱�Ƃ���߂���Ȃ��q�ǂ����������݂���̂�����ł��B
�i�U�j����ǂ���{�@����̖@�����̂��ƂŢ�q�ǂ��̌�����ᣐ����
�@�����̂́A���ǂ���{�@�F��10���́u�����̂��ǂ��v��v�����肵�A�֘A�@���Ɋ�Â��u���ǂ��{��v�����s���Ȃ���Ȃ�܂���B�����̂̂��ǂ��{��́A��Ɂu�q�ǂ��̌����ɂƂ��Ăǂ��Ȃ̂��v��_�����邱�Ƃ���ł��B�����āA�u�����̂��ǂ��v��v�͖@���Œ�߂�ꂽ�����⎖���E���Ƃ�D�荞�݂Ȃ���u�q�ǂ��̌����v��i�삵�A����𑣐i���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ����v��Ƃ��邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@���̍ہA�u�q�ǂ����i�q�ǂ��̌������j�v�̊j�ł���q�ǂ��̈ӌ��\�������ۏႳ��Ă��邩�ǂ�����_������@�ւƂ��āu�q�ǂ��̌����i��@�ցi�q�ǂ��R�~�b�V���i�[�E�q�ǂ��I���u�Y�}���j�v�̐ݒu���s���ł��B���������g�D�́A�q�ǂ��̐����ق��A������q�ǂ��̌����̗i��A����ё��i�ɂȂ�����̂ł��B
�@�u���ǂ���{�@�v�����ł͐^�́u�q�ǂ��̌����v�ۏ�͏\�S�ł͂���܂���B���{�̌���ɂ��ƂÂ��A���邢�͓Ǝ��̔��f�Œn�������̂��u�q�ǂ����i�q�ǂ��̌������j�v���߂Ă������Ƃ����߂��܂��B
�A���@�o��ƃX�P�b�`�̗��@�j���[�W�[�����h��(1)�@
�����x���@���� ���Y
�@
���߂Ă̐ԓ����z���Ă̗��ŁA�N���̓��{���ĉẴj���[�W�[�����h�ő�̓s�s�Ŗk���̃I�[�N�����h��`�ɒ������B���[�X�z�X�e���ł͗��l�A���w���A���[�L���O�z���f�[�Ȃǂ̎�҂̓��{�l��؍��l�����Əo��A�y�����L�v�Ȏ����߂������B�A������A�����̗��s�L��Ƃ��u���E��Y�Ƃ����Ă��w�̉�x�ŁA��������w���ŏo����ĉ���b�������x�̕����v���o�ɂȂ��т��c�v�Ƃ̃��W�I�����B���͑����A�����ǂ̓d�b�ԍ��ׂĎ��ȏЉ�����A�ԑg�S���҂ƃQ�X�g�Ɠ��l�̑̌���`����ƁA���̔ԑg�Ɍq���ƌ����Ă��ꂽ�B������X�P�b�`�Əo��̃G�s�\�[�h�𒆐S�̗��s�L�Ƃ������B
�@
�I�[�N�����h��w�̃Z�~�i�[�n�E�X�i�P�j
���̃X�P�b�`�����Ă���ƁA�Ō�Ȃɗ��w���̏��q�w�����������Ęb�������Ă��ꂽ�B�u�e�ɓ����œ��{�l�̗��w���Ɠ������Ă���B�ނ��A���o�C�g�����Ă��邽�߁A�[�H�͖钆�ɂȂ邪�A�ǂ�������[�H�ɂǂ����v�ƗU���Ă��ꂽ�B
�������u���肪�Ƃ��v�Ɖ������A�X�[�p�[�ňꏏ�ɐH�ނ��A�A�p�[�g�ŗ�������`���Ĕނ̋A��܂ŁA���w�����Ȃǂɂ��āA�b���ĉ߂������B
24�����߂��Ĕނ��A��A�R�l�Œx���܂Řb�����B���̌�A�^�钆�̃��[�X�z�X�e���܂ő����Ă�������B
�ʂ̃��[�X�z�X�e����K�ꂽ���A���[�L���O�z���f�[�◷�l�̓��{�l�̘b�̗ւɓ���Ă�������B�q��ŋ��̐��b�����Ă��鏗���́u���̕�����юU���Č��̒��ɓ��邱�Ƃ������c�v�Ɛ[���Ȋ�Ō����ĊF���킹���B
��x���܂Řb������A�h�ɂ̃��[�X�z�X�e���Ɍ������Ă���ƁA�X���̂Ȃ����ɂȂ��āA������̎��ɂ͐^���ÂőO�������Ȃ��Ȃ�A����̃��[�X�z�X�e���Ɉ����Ԃ��āA�ށE�ޏ��ɗ��r��g��ł�����Ă̋A��ƂȂ��Ă��܂����B
���̓��́u���邢�����ɂP�l�ŋA��悤�Ɂv�Ƒ����ꂽ�B
�@
�I�[�N�����h��w�̃Z�~�i�[�n�E�X�i�Q�j
�����Ȓ��N���������̃X�P�b�`�����Ă��ꂽ�B
�u���w���ɂ��Ă͎Ⴍ�Ȃ����v�Ǝv���Ă���ƁA�u�_�˂̖�t�ŕv�Ǝ��ʂ��Ă���A�悤�₭���q�����Z�ɓ����Ď��������̂ŗ��w�����ӂ����B��t�͂��ł��A�E��������̂Łv�Ƙb���Ă��ꂽ�B
�@���̐������ɋ������N�����̂ŁA�X�P�b�`���I����Ă���A�E�C���o���ăZ�~�i�[�n�E�X�ɓ���A�ޏ���T���āu�f�[�g�v�̖������B
�@�����A�ȑO�m�荇���Ă�����҂�A��ĉ�ɍs�����Ƃ���A�ޏ������N�̒j�������ė����B���̎�҂́A�u���X�g�T�����C�v�̃G�L�X�g���ɉ��債�A�R�����̃��P�̌�ɗ������Ă����҂������B
�ޏ����u�r�[���ł����݂Ȃ���v�ƌ������̂ŁA�ꏏ�ɓX��T�������A�����ɂ��u�s���̓X�͋֎��̓��v�ƕ��������B����Ɣޏ����A�u���̃A�p�[�g�I�v�ƒ�Ă��Ă���A�S�l�ŏ[�����������߂������Ƃ��ł����B
�@
�I�[�N�����h��w�̃V���{���^���[
�X�P�b�`�����Ă���ƁA�����̂悤�Ȓ����̗��w�����̂�������ŗ����B
�����u���`�ɂ͉Ƒ��ƃN���[�W���O�łR���ԑ؍݂������Ƃ����邪�A�����{�y�͖K�ꂽ���Ƃ��Ȃ��B�h�B�A�����A��C�Ȃɂ́A���Ѝs���Ă݂����Ǝv���Ă���v�Ƙb�����Ƃ���A�ޏ��͂����Ȃ�o�b�O���玆�����o�����B
�����āA�u���̌̋��͂��̋߂�������v�ƌ����Ȃ���A���̎��ɏZ���ƃ��[���A�h���X�������Ă��ꂽ�B
�������̎�������Ă�����q�ׂ�����A�ޏ��͉��x�����i�ƃX�P�b�`������ׂāA���炭�͑��𗣂�Ȃ������B
�@
�I�[�N�����h�̍����ٔ���
�Ԃ������K�Ɣ����̑g�ݍ��킹���������������������̂ŃX�P�b�`�����Ă����B
����ƁA���N�̏������b�������Ă��āA�u���̌����͍����ٔ����v�Ƌ����Ă��ꂽ�B
���̏����͂��炭�X�P�b�`�����Ă������A���ɉ�b�����邱�Ƃ��Ȃ��A�₪�Ďp�������Ȃ��Ȃ����̂ŁA�����A�������̂Ǝv���Ă����Ƃ���A�Ăь���āA�Ί�ł����Ȃ莄�̑O�ɗ���������o�����B
�@
���̎�ɂ́A�����ƃp�����������B
�@
�܂��ɒ����������B�v�������Ȃ��v���[���g�͊i�ʂ̖��������B
�@
�A�[�g�M�������[
�@�����X�P�b�`������̂́A���R���̌����╗�i�ɖ��͂������邩��ŁA���̓��������̎p�Ɉ��������A���������M�����ăX�P�b�`�u�b�N�Ɍ������Ă����B
�@�Ƃ��낪���炭���āA�����Ə����Ⴄ���Ƃ��N�����Ă��邱�ƂɋC�t�����B
�@�`�����ސl�����ɂȂ������̂��B�u�Ȃ��H�v�Ƃ����v�����b�������߂��B
�@�������A�u���̌����͔��p�فv�Ƌ����Ă��ꂽ�l�����āA���̓�͈�u�ɂ��ĉ������B�����ɏW�܂��Ă�l�X�̑唼�͋��炭���p���D�ƁB����Ȑl�B�����̊G���̂�������ł����킯���B
�@�G��`���Ă��鎄�����R���p�D���Ɣ��f���ꂽ���炾�낤�A�u����Ȕ��p�i������v�u����ȊG������v�ƓW���i�ɂ��ĐF�X�������Ă����l�܂ł����B
�@
�@
�܂���l�@��Ȓ��Ԃ��V���֗��������i��ҁj
�` �Ɩ�E�n��E�א�E�����搶�� �`
�����x���@�ݖ{ ���Y
�@
�@�O��A�n���m����(2023�N12��27���v)�A�Ɩ�~�q����(2022�N�W���S���v)�ւ̒Ǔ��𒆐S�ɏ����܂����B����́A����ɐ旧���ĖS���Ȃ��Q���̒��ԁA�א���V����i2013�N�S��27���v�j�A�����B����i2019�N�S��23���v)�̂��Ƃ�U��Ԃ�A�n��E�Ɩ�E�����E�א�̂S�������߂ĒǓ��������Ǝv���܂��B
�����B����́A�V�̗p�̋ՉY���Z����ɁA�q�~�ˁE�ʖ����E�ʖ������o�ĉ��R���R�ʐM���Œ�N�ސE�B���̌��2019�N�܂Ŕ��u�t������Ă��܂����B���́A��������ƍ����g�N���ŏo��A�ނ��N���������Ă����Ƃ��A�������w�K���_�W��k�C�����M�s�ŊJ�Â���܂����B���R�S���̎Q���g�ɁA���|�[�g�Ȃ��̎��ƉƖ삳���������ƁA��������́u�ݖ{�����Ɩ삳��̏����Ɋ��҂��悤�v�ƌ����Ă���A�ꏏ�ɎQ�����܂����B���̂Ƃ����߂đS���̋��E���Ƌ��Ɍ��A���̌o���͎����̍��Y�ɂȂ�܂����B
���̌�A��������͐t���̕a�C�������܂������A���̕a�C�ƌ��������A���������̖T��u���c�Ђт��v�Œ������������������ė����܂����B��N�ސE��́A���u�t�����Ȃ���A���R���ދ��̎����Lj��߁u���v�ҏW�ɂ��g����Ă�������A�u���c�Ђт��v�̊����ȂǂƂ������āA���͓I�Ɋ������Ă��܂����B
�א삳��́A�V�̗p�̍����s�����R���Z����ɁA�������R�H�Ɓi�r���T�N�Ԃ͉��R�����g�ł̑g����]�j���o�āA���R��ݔC����59�Ŏ�������܂����B�א삳��Ƃ́A�u�����Ђ܂��w�Z�v�ŏo��A���̌�A���ɍ����g�N�������Ɋւ��A����ɂ͉��R�������̒n��T�[�N������������悤�ɂȂ�܂����B�u��������R�v����A�ĂƏt�̍��h����~�j�S�����ɐϋɓI�Ɋւ��悤�ɂȂ�A1987�N���납��A�����m�������ǒ��̂��ƁA�א쎖���ǎ����A���ÍW����A���c�N������A�n���m����A���i�ݖ{���Y�j�������Lj��Ƃ��ďW�܂芈������悤�ɂȂ�܂����B���̌�A1990�N�W���̍������S�����(�q�~���)�J�ÂɌ����ĕ����������X�̋L���͓��ɑN���ł��B�����̉��R�H�ƍ��Z���ʉȐE�����͉��R�������̎����lj�c�̉��Ƃ��Č��P��A��ɂ͖��T�W�܂��ď������邱�ƂƂȂ�A�������S�����i�q�~���j�������I�����܂����B
1994�N�Q��28���ɉ��R�������̌���\���������،����`���x����̂��߂���������܂����B���̌��ǂ��悤�ɁA�R���ɂ͎O�؏���������������܂����B��������32�˂̂Ƃ��A������̒J���F����⚠�{������̑������]��ɐڂ��āA�א삳��Ƌ��ɁA�Ⴍ���ĖS���Ȃ閳�O�Ɏv����y�������̂ł����B�������A63�˂̔��،������50�ˑO��̎O������]��ɐڂ����Ƃ��A�ǂ�قǔN����d�˂Ă��A�܂��܂����c�������Ƃ�������ł͂Ȃ��������Ǝv�킸�ɂ͂����܂���ł����B
���������2019�N�S���̐V�w�������u�t�Ƃ��ďT�Q���Ζ����Ă��āA�S���Ȃ�P�T�ԑO�Ɏ��͉���ĕ��ʂɘb�����Ă����̂ɁA�]�[�ǂŋ}�����ꂽ�ƉƑ����畷���܂����B
�א삳��́A�咰���������Ă���̂P�N���܂�̓��a�����̓��X�ł��A�^���@�̂��������������A����R�ւ��s������A���ɂP�`�Q��A�u����فv�Ȃǂʼn���ċ���k�`�≪�R�����g�̘b��������A���ƕ���̎�ނ�������A�u�w�т̂Ђ�v�Ɍ��e������ȂǁA�c���ꂽ���Ԃ�搉̂��Ă��܂����B���������u�̕�����ҁv�̂悤�ɑ匩������ĕ��䂩��ޏꂵ���א삳��ł����B
�v���A�n�ꂳ��ƍא삳��͂���Ƃ̓����ɑΛ����Ď����̐��������т����悤�ł���A�Ɩ삳��Ƌ�������́A�]��ɓˑR�ɁA�����̂悤�ɐl���̕���̖����������ꂽ�悤�Ɋ����܂��B
�S���������̌���\�ł������|����ꂳ��́A�א삳��̒Ǔ��W�̊������Ɏ��̈ꕶ�i�ꕔ�����j���Ă��������܂����B
�@�̐l�̂��Ƃ��v���߂��炷�Ƃ��A�������́u�Ǔ�����v�Ƃ́A�u���҂̊肢�ƍ��݂ƈ����p���A���҂��������̂��Ƃ��S�点��v�A�܂�u���҂ƘA�т��邱�Ƃł���v�ƐS�ɍ��݂��ނ��Ƃɂ��Ă���B
�@���ꂪ�������ɂł��Ȃ��ł��邩��A�gYasukuni War Shrine�h���J��Ԃ��������Ă���̂��B���Ƃ���A�u���҂ƘA�т���v�Ƃ����V�����u�Ƃނ炢�����v�����邱�Ƃ��܂��A�������̎v�z�^���̂ЂƂƂȂ�B
�@ |
�א삳��̎����ȍ~�A���́u�̐l�ƘA�т���v�Ƃ������t�͎��̐S�Ɏh�������܂܂ł��B�u�Q�Q�Q�̋S���Y�v�̖ڋʂ��₶���S���Y�̌��ɏ���Ă���悤�ɁA�����̗����ɍא삳���������A�ꏏ�ɘA�т��Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B���̐S�̒��ɂ́A�����A���ł��A�א삳�����Ă��܂��B
��������A�Ɩ삳��A�����č���̔n�ꂳ��̎����ɍۂ��Ă��A���߂āu�̐l�ƘA�т���v�Ƃ������Ƃ��]���ɕ�����ł��܂��B���̌��ɁA�����̂S�l�̒��Ԃ���������Ă���A�u���҂̊肢�ƍ��݂ƈ����p���A���҂��������̂��Ƃ��S�点��v�A�܂�u���҂ƘA�т���v�Ƃ����V�����u�Ƃނ炢�����v�����H���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�܂��A�ނ�Ƌ��ɔ|���Ă����u�N���X�W�c�Â���v�u�w�N�W�c�Â���v�Ȃǂ̍l�����́A���E��ނ�����ł��A�������n���ƒ���Ȃǂ̏�ł���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�@
�@
�����邱�Ƃ́@����悵�@����
�\�\�\���t ����b���q�搶���Âԁ\�\�\
���R�x���@���� �͎q
�@
�����邱�Ƃ́@����悵�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����V���i���{�ŏ��̃g�[�L�[�f��ēł���o�l�j
�@����b���q�搶�͎���̕ǂɏ���ꂽ���̌��t�����E�̖��Ƃ��Đ��U�������A2024�N�P��22���ɐl���̖������낳�ꂽ�B���N93�B
�@�搶�́A�R�Z�ڂ̋Ζ��Z�ł���ʓ����Z�ŁA����̋��ȒS�C�A�R�N���i�R�d�j�̒S�C�Ƃ��Ă��w����������A���̍��Z���ꋳ�t�Ƃ��Ă̔����J���Ă����������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����t�ł���B
�@���Ƃł́A�l���A�����A�������邱�Ƃ��������߂�ꂽ�B�������̓����ł����邪�A���ɂ���������ʂ����������B�������̔������E���Ȃ���[���̂����������������Ă�������B���ɕ��w��i�w�K��̊��z���̂������͕K���菑���v�����g�Ƃ��Ď������ɕԂ��ꂽ�B�v�������Ȃ����z�ɋ����A�V���Ȏ��_��^�����č�i�ւ̗������[�܂����̂���������Ɠ����ɁA���ꂪ�\�z�O�̋��F����̂��̂ł���ꍇ�������A���F�̐V���Ȗʂ�m���ĉ��x�����������o��������B
�@�N���X�S�C�Ƃ��Ă��A�������ʂŎ������̔��������߃N���X�̍��ӂ����グ��悤�ɏ\�����Ԃ������Ă�������t�������Ă�������B�v���o�[���̂́A�w���ՍP��̂R�N���N���X�����B�ӋC���݂��肪��
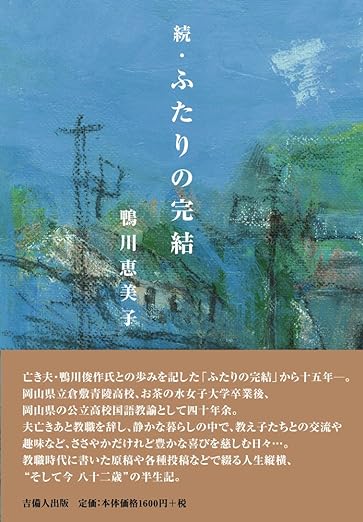
�s���A�ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ��B�������A�搶�͐��}�Ɍ��_���o�����悤�Ƃ͂��Ȃ��B�������͘b�����������Ȃ��B���������̕���ē𒆐S�ɊF�̔[���ł��钅�n�_���m�F���Ă͑O�i�B�����̑I���헧���҂ւ̔�����D������Ȃ��犮������������́A�唚�Ɣ���̒��A���������ł�肨�������Ƃ����B�����Ə[�����A�����đ傫�Ȏ��M�������炵�Ă��ꂽ�B����ɋ��F�ւ̐M���͐[�܂�N���X�̒c�����m�M�ł����̂��B�����̋ʓ����Z�ɂ��Đ搶�́A�w���ɍ������w�Z�x�w����I�Ƃ������A�݂�Ȃ̈ӌ��i���E���E���k�j��������悤�Ƃ���A���ꂾ���ɖZ�����A�������ӌ����o�������A�ӗ~�I�x�ƌ����Ă�����B�i�����w���E�ӂ���̊����x�j
�@�܂��߂Ɏ����ōl������������̌��t�Ō�邱�ƁA���҂̌��t�Ɏ����X�����ՂɑË�����̂ł͂Ȃ��[�������܂Řb���������ƁA���Ԃ̂����邱�Ƃ�ʓ|�������炸�ɂ�葱���邱�ƁA���������ߒ����Ƃ����Ă����l�ƌq�����Ă�����̂��Ƃ������ƁB�搶�́A�w�Z�����̂������ʂŁA��������M���Č�����Ă�������Ȃ���A�搶�̌��t�ƍs���ł���������Ă����������B���Z���@38�N�ԁA�ہA���U��ʂ��āu��v�ɂ��̐����������т��ʂ��ꂽ�̂��Ǝv���B�搶���c���ꂽ�Q���̒����w�ӂ���̊����x�w���E�ӂ���̊����x�����߂Ĕq�ǂ��Ă��̎v�����������Ă���B
�@
�@
��Q��V���R���j�T�K(�ʎZ52��)�̂��U��
�����x���@���@�@��
�@
�h���R�Ƌ��ɐ������R���Ɣɉh���Âԏh�꒬�ɓ��{�l�̌����i��K�˂闷�g
���挧�q���h�𒆐S�ɂ����n���ēx�K�˂�
����̊��́A2016�N�ɁA�̒��c�[�i�搶���̃����C�N�łł��B�O��D�]�ł����̂ōēx��悵�܂����B�O��Q�����ꂽ�l�����ЎQ�����Ă��������A�q�����̖��͂��Ĕ������Ă������������Ǝv���܂��B
��ȖK�����ȒP�ɏЉ�܂��B
�w��䌴�W���x
�@�q�������S�n����k����Rkm�Ɉʒu����䌴�W���́A�R�Ɉ͂܂ꂽ�����ȏW���ŁA���Ɨ��l�̉B�ꗢ�Ƃ������A���a42�N�ɔ䌴�g���l�����J�ʂ���܂œk���ōs��������u�Z�ړ��v�������B��̓��ł����B���̘Z�ړ��ɉ��������������Ȃ������̏W�����U�����Ǝv���܂��B���̏W���ɂ́A�u�����ƏZ��v�i�����͊����j�A�z50�N����Ö��ƌQ�A���a
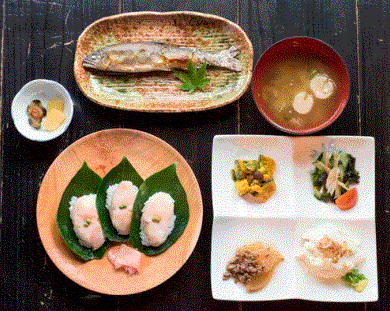
�����Ɍ��Ă�ꂽ�u�䌴�����فv�A�W���������u���R�_�Ёv�A���ԏ����A�Y�Ă������Ȃǂ��������Ă��܂��B2004�N�Ɂu���挧�`���I�������Q�ۑ��n��v�ɑI�肳��Ă��܂��B
�U��̌�́A2020�N�I�[�v�������Ö��ƃJ�t�F �a���i�̂ǂ��j�ŐH���ł��B�q�������Y�̐V�N�ȐH�ނ��g�p���������L���ȋ��y�������y���݂����Ǝv���܂��B�����͑傫�Ȉ͘F��������A�S���ق��Ƃ���悤�ȕ��͋C���}���Ă���܂��B
�w�q���h�x
�Q�Ό��̓��ł��������q�������i�����X���j�ƁA���O�X���̍����n�_�ɂ���A�q���h�́u�q�������v�̏h�꒬�ł����B�]�ˎ���ɂ́A�Q�Ό��ō]�˂ւƌ���������˂̍ŏ��̎~�h�ł���A�ˎ�̏h����x�e�̏�ƂȂ�䒃�����s���A���D�ꂪ�u����Ă����v���ł����B�����ɉ����܂����݂ɂ͏h�꒬�Ƃ��ĉh���Ă����������Â��钬���̌����⓹�W�������c���Ă��܂��B���w��d�v�������́u�ΒJ�ƏZ��v�A�u�����o�X�v�A�u���͍��ȉf��L�O�فv�A�u�z�K�_�Ёv�ȂǁA�����������U����y���ނ��Ƃ��ł��܂��B�ʂ艈���̖��Ƃɂ͐��ʂ������A�g���̂܂��h�Ȃ�ł͂̕���Ŋό��q�����o�}�����Ă��܂��B
�ΒJ�ƏZ��
�ΒJ�ƏZ��́A�q���h�ɂ���u�ߑ�a�����z�v�ŁA�q���h�ŁA�ł��傫�Ȍ����̈�ł��B
���̐ΒJ�ƏZ��́A�����������吳����̓���ŁA�M���@�c���߂��R�ђn��̐ΒJ�`�l�Y�����z���c�������̂ŁA���܂��܂ȗl���������ɒ��a�������s�ȓ@��ł��B�剮�A�뉀�①�Ȃǂ������̂܂܂ŕۑ�����Ă���A�ߑ�a�����z�̑�\�I�Ȍ����ł��B2009�N���́u�d�v�������v�Ɏw�肳��A�뉀��2008�N�Ɂu���̓o�^�L�O���v�Ƃ��ēo�^����A2010�N�ɂ͒��挧�̎w�薼���ɂ��w�肳��Ă��܂��B
�������o�X
�q���h�ɂ�����j�I�������̈�ŁA�ΒJ�Ƃ̕��ƂƂ��Đ�O�Ɍ��Ă�ꂽ�������ŁA2000�N�ɍ��́u�o�^�L�`������(������)�v�ɓo�^����܂����B
�P�K�͏��@���ŁA�������a���뉀�ɖʂ������~�́u�i���E���H���� �C�F�R�F�v�Ƃ��āA���Ĕ������H�ׂĔ�����������Ȑl�C�X�|�b�g�ł��B
���݂͒q���o�g�Łu�ɓ��̗x�q�v��u�⏥�v�Ȃǂ��ē����w���͍��ȉf��L�O�فx�Ƃ��Č��J����Ă��܂��B
�m�����h�ԏ��i�q�����h�c�{�����c�ԏ��j
1941�N�ɐΒJ�ƏZ��̐^�������Ɍ��Ă��A���h�ԏ��Ƃ��č��������Ŏg���Ă��܂��B���a���㏉���Ɍ��Ă�ꂽ���h�ԏ����z�Ƃ��Ĕ��ɋM�d�ŁA�m�����z�̔��������e�����j�I�i�ςɊ�^���Ă��邱�Ƃ���A2000�N�ɍ��̓o�^�L�`�������ɓo�^����܂����B
����̊F����A���Ă̗Ε��𗁂тȂ���A���a�̔_�����i�ƐH�������\���A���j����h�꒬�̎U����y���݂܂��B����F�l�̎Q�������҂����Ă���܂��B
�@
�@
 ����������������������������
����������������������������
���V�^�R���i�̂T�ވڍs�ɂ��A���̒��ł́A�}�X�N���p���`���ł͂Ȃ��Ȃ�܂������A�a�@��JR�Ȃǂ̌�ʋ@�ւɏ��Ƃ��Ȃǂ́A�܂��}�X�N�͎�����܂���B���͉ԕ��ǂ�����̂ŁA�}�X�N���p�͂������炭���������ł��B�܂��A�R���ɂȂ��Ă������̉Ƒ���ߏ��̕��̃R���i�����������Ă��܂��B�R���i�����͖Y�ꂽ���ɂ���Ă��銴���Ȃ̂ŁA�}�X�N���p���K�v�ɉ����đ����邱�Ƃ��Ǝv���܂����A�A���̎�������邱�Ƃ��ȂƎv���Ă��܂��B���w�Z�̕��́A�قڃR���i�O�̏ɖ߂��Ă��Ă���A�C�w���s��w���ՂȂǂ̍s���͈ȑO�Ɠ����悤�Ɋ����ł���悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�������u�t�����Ă���w�Z�ł́A�Y�N��A���Əj���A�����}��Ȃǂ̈��݉��N12�����ĊJ���ꂽ�̂ŁA�v���Ԃ�Ɂi�T�N�Ԃ�ɁH�j�Q�����Đe�r��[�߂܂����B�����t�̐l���ٓ��ł́A��N�����̂��߂ɁA��N�ސE�̕��͂��Ȃ��̂ŁA�ސE�͎�N�ސE�̕�����ł����B�܂��A�Ǘ��E�̖�E��N�Ƃ������x���X�^�[�g���āA�Ǘ��E�����������劲���@�E�w�����@�֓]�Ƃ����`�ł̐l���ٓ��ł����B�ĔC�p�̓]�͐V���ɂ͌f�ڂ���Ȃ��̂ŁA�ȑO�����l���ٓ��̓�����������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�����͍�N�̂V�����獂�ދ��̉��W�ɂȂ�A173���`175���܂ł͍Z���̎�`���݂̂ł������A����176���ł͏��߂ĕҏW�S�������Ă��܂��B�ŋ߂́A�����쐬�̓��[�h���g�����Ƃ������Ȃ��Ă����̂ŁA�ꑾ�Y�ł̕ҏW��ƂɈ���ꓬ���Ă��܂��B���e�x���̏t�̌𗬉�͍�N���畜�����ĂQ�N�ڂō���͂��ׂĂ̎x���Ō𗬉�J�Â���܂����B����g�搶�̌��N�̑���20�N�ȏ㑱���Ă���s���ł����A�O��̉���̂Ƃ������ǂ̎�Ⴂ�ňē��`���V���ł����A�����f�����������܂����B���]��A���������Ă��܂����A�����Ɠ��N��̕����S���Ȃ�̂��h�����̂ł����A��y�≶�t�̕����S���Ȃ���ꍇ�͂����Ɛh�����̂ł��B���̕��̕����Y�ꂸ�ɁA85�̍��ދ��̒������j����܂ł͌��C�ɉ߂����Đ��������Ǝv���������̍��ł��B�i�ݖ{�j
������������������������������������
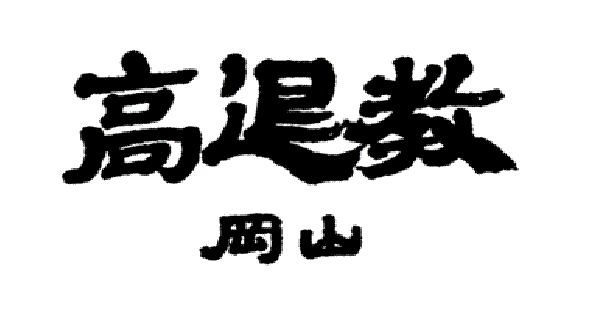
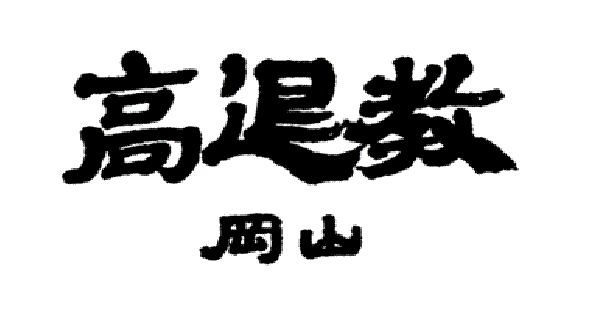
 ��
��
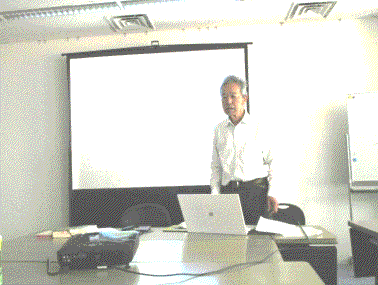 ���������܂����B���������m���Ă���悤�Œm��Ȃ��p���X�`�i���B�Η��̍����Ƃ����A���_�����E�L���X�g���E�C�X���������ꂼ��̌n���A�����p���X�`�i���̗��j�i�L���X�g�����͂ɂ�郆�_�������Q�A�ߑテ�_���l�̌o�ϗ́A��ꎟ����̃A���u�̓Ɨ��E���_�����k�̃V�I�j�Y���^���A���풆�̃i�`�X�̃��_���l��Ő���A�����̍��A�ɂ��p���X�`�i�����āA�C�X���G���̗̓y�g��A�K�U�n��̊�@�Ȃǁj�ɂ��Ă�������b���Ă��������܂����B�����ɂ��������n��҂̐��ɂ�������悤�ɁA�o���̑Η��ӎ��͋~���������Ƃ��v���܂����A���Ԃ�ŊJ����ɂ͍��ې��_��傫�����߂Ă������Ƃ��K�v�ł���A�o���ƑΓ��ɘb�̂ł���͂��̓��{�̖������d�v�ł͂Ȃ����Ƃ̎w�E����ۓI�ł����B
���������܂����B���������m���Ă���悤�Œm��Ȃ��p���X�`�i���B�Η��̍����Ƃ����A���_�����E�L���X�g���E�C�X���������ꂼ��̌n���A�����p���X�`�i���̗��j�i�L���X�g�����͂ɂ�郆�_�������Q�A�ߑテ�_���l�̌o�ϗ́A��ꎟ����̃A���u�̓Ɨ��E���_�����k�̃V�I�j�Y���^���A���풆�̃i�`�X�̃��_���l��Ő���A�����̍��A�ɂ��p���X�`�i�����āA�C�X���G���̗̓y�g��A�K�U�n��̊�@�Ȃǁj�ɂ��Ă�������b���Ă��������܂����B�����ɂ��������n��҂̐��ɂ�������悤�ɁA�o���̑Η��ӎ��͋~���������Ƃ��v���܂����A���Ԃ�ŊJ����ɂ͍��ې��_��傫�����߂Ă������Ƃ��K�v�ł���A�o���ƑΓ��ɘb�̂ł���͂��̓��{�̖������d�v�ł͂Ȃ����Ƃ̎w�E����ۓI�ł����B
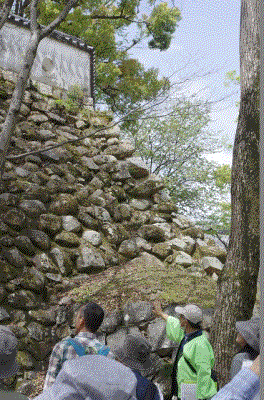 �܂����B�ȉ��Ɏ�Ȋ��z���Љ�܂��B
�܂����B�ȉ��Ɏ�Ȋ��z���Љ�܂��B
 �Ȃ̂ɁA�����m�炸�ɐ����Ă����ƒɊ��B�Ί_�������N���i��C�������āj�c����Ă���I�Z�ؐς݂��ǂ̂悤�ɍl���Ċ��������Ă������̂��B����������������ł����B�i������Î}����j
�Ȃ̂ɁA�����m�炸�ɐ����Ă����ƒɊ��B�Ί_�������N���i��C�������āj�c����Ă���I�Z�ؐς݂��ǂ̂悤�ɍl���Ċ��������Ă������̂��B����������������ł����B�i������Î}����j
 ���Ƃ͂킩��܂������A��������ł����B���ې��_�Ő����������ɂȂ邱�Ƃ��c�B�i���c�G�b����j
���Ƃ͂킩��܂������A��������ł����B���ې��_�Ő����������ɂȂ邱�Ƃ��c�B�i���c�G�b����j
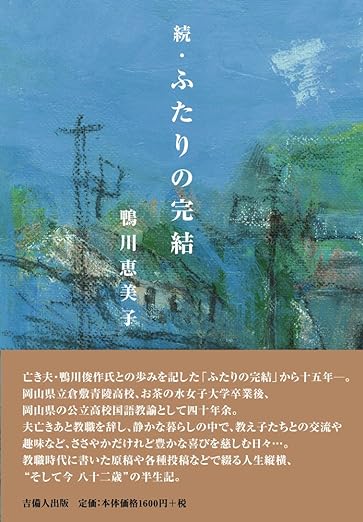 �s���A�ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ��B�������A�搶�͐��}�Ɍ��_���o�����悤�Ƃ͂��Ȃ��B�������͘b�����������Ȃ��B���������̕���ē𒆐S�ɊF�̔[���ł��钅�n�_���m�F���Ă͑O�i�B�����̑I���헧���҂ւ̔�����D������Ȃ��犮������������́A�唚�Ɣ���̒��A���������ł�肨�������Ƃ����B�����Ə[�����A�����đ傫�Ȏ��M�������炵�Ă��ꂽ�B����ɋ��F�ւ̐M���͐[�܂�N���X�̒c�����m�M�ł����̂��B�����̋ʓ����Z�ɂ��Đ搶�́A�w���ɍ������w�Z�x�w����I�Ƃ������A�݂�Ȃ̈ӌ��i���E���E���k�j��������悤�Ƃ���A���ꂾ���ɖZ�����A�������ӌ����o�������A�ӗ~�I�x�ƌ����Ă�����B�i�����w���E�ӂ���̊����x�j
�s���A�ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ��B�������A�搶�͐��}�Ɍ��_���o�����悤�Ƃ͂��Ȃ��B�������͘b�����������Ȃ��B���������̕���ē𒆐S�ɊF�̔[���ł��钅�n�_���m�F���Ă͑O�i�B�����̑I���헧���҂ւ̔�����D������Ȃ��犮������������́A�唚�Ɣ���̒��A���������ł�肨�������Ƃ����B�����Ə[�����A�����đ傫�Ȏ��M�������炵�Ă��ꂽ�B����ɋ��F�ւ̐M���͐[�܂�N���X�̒c�����m�M�ł����̂��B�����̋ʓ����Z�ɂ��Đ搶�́A�w���ɍ������w�Z�x�w����I�Ƃ������A�݂�Ȃ̈ӌ��i���E���E���k�j��������悤�Ƃ���A���ꂾ���ɖZ�����A�������ӌ����o�������A�ӗ~�I�x�ƌ����Ă�����B�i�����w���E�ӂ���̊����x�j
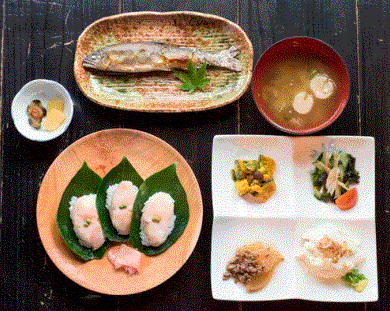 �����Ɍ��Ă�ꂽ�u�䌴�����فv�A�W���������u���R�_�Ёv�A���ԏ����A�Y�Ă������Ȃǂ��������Ă��܂��B2004�N�Ɂu���挧�`���I�������Q�ۑ��n��v�ɑI�肳��Ă��܂��B
�����Ɍ��Ă�ꂽ�u�䌴�����فv�A�W���������u���R�_�Ёv�A���ԏ����A�Y�Ă������Ȃǂ��������Ă��܂��B2004�N�Ɂu���挧�`���I�������Q�ۑ��n��v�ɑI�肳��Ă��܂��B
 ����������������������������
����������������������������