「牽引車両」の
操縦
「牽引車両」は連結部(キングピン・ヒッチボール)で、
折れ曲がる構造で在る為に独特特有の動きをしま
す。トレーラーの向きを変えるためにトラクターの向きを変えます。ト
ラクターの向きを変えるためにハンドルを回します。ここで考えてみてください。ハンドル操作に対してトラクターが向きを変えるためには、トラクターが前後
進す
る必要が在ります。望みの(必要とする)折れ角に達するまで動く距離が必要なのです。このように牽引車両には「構造的な動作遅れ」があるため、トラクター
単体に比べると、
曲
がり方がハンドル操作に対して大幅に遅れるような感じになります。
右左折は、トラクター単体では曲がる方向にハンドルを切り、戻せば完了です。しかし、けん引車では曲がる方向にハンドルを切るのは同じですが、戻す際に
一旦逆
方向にハンドルを切り、また戻すという操作になります。その分、ハ
ンドル操作が忙しいのです。
そして、運転する際は、常にトラクターとトレーラーの動きを頭に置きながら運転しなければなりません。ハンドルを切るとまずトラクターが曲がって次にト
レーラー
が曲がる...などと考えると複雑になるので、もっと簡単に考えてみます。
「牽引車両」の特徴は、トレーラーの動きをトラクターで
コント
ロールするところですが、構造的に見ればトラクターの後輪がトレーラー単体車両の操舵輪に相当するということです。もっと厳密に言えば、連結部分のキング
ピン(又は、ヒッチボール)がトレーラの操
舵作用点になります。上手いトレーラー牽きとは、常にトラクタの後輪とトレーラの後輪の位置関係をイメージしながら運転している筈です。
1.直進
 |
トラクターの後輪がトレーラーの操舵輪に相当する訳ですが、トラクターの後輪はトラクター本体に不可
分で平行で有る事を考えると、「トラクター本体の向き」でトレーラーをコントロールしているというイメージを持つ
とよいでしょう。
つまり、トラクター単体の場合はハンドルを回すことで「前タイヤの向き」を変えますが、「牽引車両」
の場合はハ
ンドルを回すことで「トラクターの向き」を変える、と考えます。「牽引車両」のメインはトレーラーの方で在り、トラクターは
進行方向を決めるためのマシンであるということです。そして、注目すべき点は、当たり前ですがトラクターは動
きながらしか方向を変えられないことです。つまり、単体車両では据え切りができますが、けん引車では方向が決まるまで動く必要がある(据え
切りしても進行方向はまだ決まらない)ということです。
|
直進状態では、トレーラーならではの挙動を意識する必要性は余りありません。ですが、「牽引車両」は、トラクター+トレーラーを足した全長が在る訳です から、日 常の足で使っているトラクター単体での走行とは、その全長に留意した運転が不可欠です。交差点や踏切への進入や路外施設への入場の際にも、その全長の停車 余地を確認しない限り「牽引車両」を進めてはなりません。更に、我々の牽いているキャンピングトレーラーはトラクターよりも車幅が広い場合が多いので、ト ラクターが通過出来てもトレーラーが接触する可能性もあります。全長と同時に全幅への心遣いも必要とされます。それと・・・、直進には限定されませんが、 トレーラーの全高は私共が普段乗っている自動車より高いので、道路の高さ制限には注意が必要です。又、これは私だけの経験かも知れませんが、連結部を跨い だり潜ったりして通行する(危険な)歩行者もいますので、発進の前には連結部への注意も不可欠カモ知れません。
|
直進状態では、トレーラーを殆ど意識しなくても良いのですが、カーブでは、トラクターとトレーラーが折れながら曲がる為、トラクターの作る内輪差
とトレー
ラーの作る内輪差を常に意識しなければ成りません。このトラクターとトレーラーの作る各々の内輪差の大きさは、トラクターのホィールベースの長さや、キン
グピンからトレーラーの車輪までの長さや、回転するカーブの半径に応じて異なるため、実際に運転して体得するしかあ
り
ませんが、トレーラーが長い程、カーブを小回りする程、大きく成る事は当然です。又、5thトラベルトレーラーでも大型貨物トレーラーと比べてトレーラー
の車軸はセンターアクスル寄りなので、トレーラー車軸以降のリヤオーバーハングが右左折時に反対方向に突き出す事にも充分な注意が必要です。これも同じ
く、リヤオーバーハングが長い程、カーブを小回りする程、大きくなります。
一般的に(トレーラーを牽き始める前までの私自身も)免許取得時の知識としてオーバーハングの危険は知っていても実際に大きく車線を超えて突き出してく ると云う認識が無いドライバーが多いのです。右左折の前の直進状態の際に、後続車の動向も注視してリヤオーバーハングで引っ掛けない様に注意しなくては成 りません。又、交差点では停止線を守らない不届き者(トレーラーを牽き始める前までの私自身も残念ながらそうでした)が多いので、曲がって行く先の安全も 充分に確認しないと交差点の真ん中で身動きが取れなくなる恐れもあります。
一般的に(トレーラーを牽き始める前までの私自身も)免許取得時の知識としてオーバーハングの危険は知っていても実際に大きく車線を超えて突き出してく ると云う認識が無いドライバーが多いのです。右左折の前の直進状態の際に、後続車の動向も注視してリヤオーバーハングで引っ掛けない様に注意しなくては成 りません。又、交差点では停止線を守らない不届き者(トレーラーを牽き始める前までの私自身も残念ながらそうでした)が多いので、曲がって行く先の安全も 充分に確認しないと交差点の真ん中で身動きが取れなくなる恐れもあります。
ハンドルを早く切りすぎればトレーラー後輪は縁石に乗り上げ、切り遅れるとトレーラー後輪は縁石から離れてしまいます。キャンピングトレーラーを3台乗
り継いで、しかも、順番に大型化してきた私ですが、最初の全長5.6mのセンターアクスル式の英国製キャンピング・フル・トレーラーの頃は内輪差への配慮
も余り要らず、トラクター単体と同じ気分で曲がっても縁石等との接触は経験せずに済んでいました。が、トレーラー全長が7mに成った頃から、内輪差を意識
しないと危ない目に遭う事が身に染みて判り始めます。そして現行の5thトラベルトレーラーに至っては、日常とは別世界の内輪差体験を繰り返す羽目に陥り
ます。何となく雰囲気で曲がり始めのタイミングを取っていると、何度と無く縁石や電信柱や民家の軒先を引っ掛けそうになります。雰囲気では無く曲がり始め
るタイミングの見極めが必要と成ります。
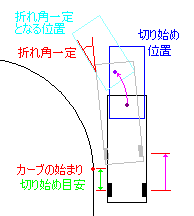 |
トラクター単体で左折するときは、後輪がコーナーのカーブに差し掛かったときハンドルを切ります。それ以前にハンドルを切ると内輪差で接輪する恐れが在り
ます。「牽引車両」でも同じで、トレーラー後輪がコーナーのカーブに差し掛かった
ときハンドルを切ります。ですが、ハンドル操作に対してトレーラーが曲がり始めるには、「構造的な動作遅れ」があるので、若干手前でハンドル
を切り始めなければいけません。
「牽引車両」の場合、厳密な切り始めるポイントとは、トレーラー後輪がカーブの始まりから、「ハンドルの切り
始め位置からトラクターとトレーラーがコーナーのRに対応した折れ角に達するまでに進む距離」よりも、少し短めの距離だけ手前です。「少し短め」というのは、対応した折れ角に達するまでの間にも若干トレーラの向きが変わるため、幾何学的に見ると、きれいにカーブに沿うには、トレーラ 後輪が「カーブの始まり」を過ぎてから折れ角を一定に維持する必要があります。ですから、厳密には、その分距離が短くてよいということです。 |
「牽引車両」はトラクターに加えてトレーラーの分だけ長いのです。切り始めるタイミングを掴むには、「牽引車両」の長さに対する慣れが必要でしょう。微
妙な調整
が必要なのは仕方がありません。また、左ミラーで見て、トレーラ後輪の位置がつかめることもポイントになってきます。こういうところで、適性検査で深視力
をやる意味がでてくるのでしょ
うか。
まずは、トレーラの後端から30cmがミラーでどのくらいに見え
るのか、確認しておきましょう。
そして、練習所では「ミラーに頼るな」と言われますが、初めはミ
ラーを見ながら曲がってみましょう。その方が早く車両感覚がつかめます。「ミラーに頼るな」というのは、曲がっている間ミラーばかり見ていては前方の安全
確認ができないので危険だという意味です。
カーブによってアール(R:半径)が異なるので、「このくらいのカーブなら、縁石からトラクタをこのくらい離せば、トレーラの後ろが縁石から30cmく
らい離れる」という感覚を体得することが先決です。慣れてくればミラーをちらちらと見て確認するだけで曲がれるようになります。まったくサイドミラーを見
ないで30cmを保つことができればたいしたものですが、巻き込み防止の意味で安全確認のためにちらちらくらいは見た方がいいです。また、一般道ではまれ
にアールが一定でないカーブがあるのも事実です。このようなカーブでまったくサイドミラーを見ないと、トレーラの後輪を擦ったり乗り上げたりすることにな
りかねません。
 |
大型トラックでは一般的に左サイドミラーは上下に二つ付いていて、上が普通の左サイドミラー、下が左サイド補助ミラー(巻き込み防
止用)でより広範囲が見える広角ミラーになっています。RAM君の場合はトラックと云っても所詮普通車なのでミラーは1つです。トーイングpkgオプショ
ンに設定されているトーイングミラーだと、左下隅に広角ミラーが付いています。交差点を曲がる時等は普通のミラーではトレーラーの側面しか見えませんが、
広角ミラーの方には辛うじてトレーラーの左後端を捉える事が出来ます。但し、広角ミラーの宿命で小さくしか映りませんから、見難いですが無いよりはマシと
云った感じです。 |
|
 (夜間の)ルームミラー内蔵モニター |
尚、後方視界はルームミラーに内蔵した5インチディスプレーで得ています。進路変更の時など左右のミラーで見えない部分を補います。かなり広角な画角な ので小さくしか映りませんが、大体左右ミラー下部の補助ミラーと同じ位の大きさに映りますので、その大きさで距離感を認識するしか在りません。(後退の 際、真下の情報って思いの外、役に立たないので、後方視界に重点を置いています。) |
左折をするとき、ハンドルに意識を集中すると、ぎこち無い運転になります。
縁石に沿って曲がっているとき、トラクタは縁石と平行になっているような感じ(厳密には後輪の位置だけが平行)で走ります。トラクタ本体に意識を集中
し、トラクタを縁石から一定間隔に保つようにコントロールするのです。前頁で述べたように「トラクタ本体の向きでトレーラをコントロール」するというイ
メージが
身に付けば、トレーラ後輪を縁石に沿って走らせることは易しくなるはずです。
|
「牽引車両」はバックの際には逆にハンドルを切る・・・と云われています。確かに、そ
うなのですが、実際には少し違います。「牽引車両」はトレーラーの挙動を中心に移動します。後にも触れますが、トラクター全体がトレーラーの操舵輪(兼、
駆動輪)として働きますので、取り敢えず、「きっかけハンドル」を与えてトレーラーを後退させたい方向にトラクター全体を回す必要が在るのです。この
「きっかけハンドル」を「逆ハン」と呼ぶ人も居ます。尚、ドーリー等を介してトレーラーを連結した「牽引車両」や、トレーラーを2台重連にした場合は、屈
曲の関節が2つ在るので「きっかけハンドル」は、逆の逆で、普通に回すそうです。
一般的に、トレーラが長いと前進が難しく後退は簡単、トレーラが短いと前進は簡単で後退が難しい、と言われます。後退の際、トレーラが短いと折れる速さ
が速く、コントロールし難い為です。私自身の経験でも、最初の牽引免許不要トレーラーの時は基本の直線バックでも真っ直ぐバックしないし、屈曲バックの際
は予想外に大きく折れ込んで屈曲バックのコントロールには苦労しました。その後の2台目のトレーラーでは、万事バランスが取れていて、運転が上手くなった
と大きく誤解していました。3台目の現在のトレーラーでは、前進右左折では内輪差に苦しみ、狭い場所での屈曲後退では曲がらなくて困っています。
後退に於ける修正のとは、トレーラーが右に曲がった時はハンドルを右に、トレーラーが左に曲がったときにはハンドルを左に回します。これはトラクター単
体の場合と
逆で、初めに、曲がった方向と同じ方向にハンドルを回す必要があります。当に「きっかけハンドル」そのものです。折れ修正を通して「牽引車両」はバックの
際には逆にハンドルを切る・・・と云うのが少し違うと説明します。
トラクターに対してトレーラーが右に曲がった場合です。
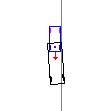 |
後退中、トレーラーが右に曲がりました。これを一直線の状態に戻しま す。 (以下の直線バックと異なり、単にトラクターとトレーラーを真っ直ぐに戻すだけです。) トレーラー後部が右に向いた場合、トレーラーの操舵輪を右に回せば良いのですが、
トレーラーの操舵輪はトラクターの後輪なので、トラクターの後輪を右に向かす為に、 トラクターの頭を左に向かせる必要が在る訳です。 |
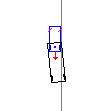 |
トラクタの前部を左に向かす為には、ハンドルを右に
回し、そのままバックします。
(「きっかけハンドル」の状態です。) |
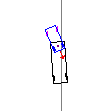 |
すると、トラクタの前部は左(トラクターの後部は右)を向きます。
ちょうどトラクターを反対側に振った形にな ります。 その間も、トレーラ の向きが少しずつ変わり修正されていきます。 |
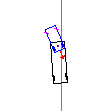 |
そして、トレーラーの方向が修正される直前に、 トラクターの前部を右(トラクタの後部を左)に振って(つまり、ハンドルを左に 回して) トラクターとトレーラーが一直線になるまで戻します。 |
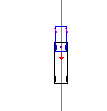 |
トラクターとトレーラーが一直線になっても、 トラクターのタイヤはまだ左を向いていますので、 ハンドルを右に回して直進状態まで戻せば折 れの修正は完了です。 |
| トラクターのハンドルは、右、左、右とハン
ドル操作を行いましたが、トラクター全体は左に向き一直線に戻っただけです。トラクター単体だけの場合だと、後側が右に向くと、左側にハンドルを切って、
トラクターの前側を左に向かせ戻すだけです。文章にしても分かり難いままかも知れませんが、「牽引車両」の挙動を理解する上でトラクターのハンドルと云う
考え方をしたら混乱するだけです。大多数のトレーラー牽きの皆さんが云われる通り「『牽引車両』は『トレーラー』を主体として考えるべきで、『トレー
ラー』の操舵輪は『トラクター』の車体全体と思うべし」に行き着く訳です。 |
|
バックと言えば、先ず直線バックが出来る事が基本で
しょう。真っ直ぐバックする事など簡単だと思うでしょうが、実際には上手くいきません。運良くトラクターとトレーラーが一直線の状態からバックを始めて
も、路面の傾きや凹凸、カプラー部の遊び等々が影響して徐々に曲がっていってしまうものです。これは前述の通り、短いトレーラーほど難しく、長いトレー
ラーほど簡単な事です。短いトレーラーは先程の種々の障害で容易く、急激に曲がっていってしまうからです。
上では「折れ修正」として、単にトラクターとトレーラーを一直線にする修正としましたが、今度は定まった進行方向に向かって直線に沿ってバックする為の 修正(直線バックのライン修正)とします。
上では「折れ修正」として、単にトラクターとトレーラーを一直線にする修正としましたが、今度は定まった進行方向に向かって直線に沿ってバックする為の 修正(直線バックのライン修正)とします。
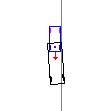 |
「牽引車両」は画像中央の直線の左側を真っ直ぐにバックしています。 しかし、後退中トレーラーが右に曲がってしまいました。 左側に沿ってバックすべき直線から逸脱しかかっています。 |
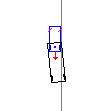 |
ハンドルを右に回し、そのままバックしま
す。
「きっかけハンドル」の状態です。「折れ修正」と同じです。
|
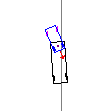 |
トレーラーの操舵輪であるトラクター全体を左に振った状態です。 |
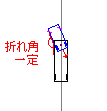 |
トレーラーがラインとやや平行になる処で、 ハンドルを直進状態より少し左に 回し、 トラクターとトレーラーの折れ角を一定に保ちます。 |
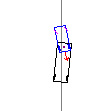 |
この状態でバックを続けると、トレーラーが右から斜めにラインに近づきます。 ここで、更にハンドルを左に切ります。 |
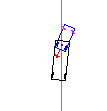 |
折れ角一定から、一直線、そして、トラクターが反対側(右)に振る形にします。 |
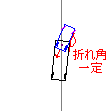 |
トレーラーに対してトラクターが右に折れたら、 ハンドルを真っ直ぐより少し右に 切り、 右に折れた折れ角を一定に保ったままバックします。 |
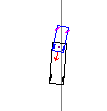 |
タイミングを合わせて、更にハンドルを右に切り、「伸ばし」にかかりま
す。 |
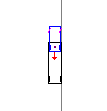 |
トラクターとトレーラーが一直線になっても、 トラクターのタイヤはまだ右を向いていますので、 ハンドルを左に回して真っ直ぐに戻せばラ イン修正完了です。 |
画像は大袈裟な振れ幅を取っていますが、実際には、こんなに大きな振れ幅を取る必要は在りません。
尚、センターアクスルなトレーラーでは折れ角一定の釣り合いは、この僅かな折れ角では取れないので
この方法に依る直線バックのライン修正は出来ません。一旦、大きめの折れ角を付け、その角度を小さ
くしつつラインに載せる超高等テクニックが必要です。
尚、センターアクスルなトレーラーでは折れ角一定の釣り合いは、この僅かな折れ角では取れないので
この方法に依る直線バックのライン修正は出来ません。一旦、大きめの折れ角を付け、その角度を小さ
くしつつラインに載せる超高等テクニックが必要です。
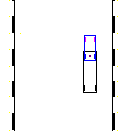 |
同じテクニックを使って、後退幅寄せもクリア出来ます。私自身も練習場で試しましたが、何度やっても上手く収束させる事が出来ませんでした。後退幅寄せ が出来るという事は、 バックでの進路コントロールが体得出来ている証でしょう。(広島の知人は教習所で、これを一発でこなしたそうです。だから、彼はバックが上手いのだろ う。)自動車運転免許試験場の検定員は牽引3種とか4種を取得しているそうですが、3種から後退幅寄せ、4種ではS字バックが課題にあるそうです。何回も 検定に通ったので、検定員の方と良く話をしましたが、その耳学問です。(尚、検定員の方は公道で「牽引車両」を走らせた事は無いそうです) |
(4)折れ曲がり後退の特徴
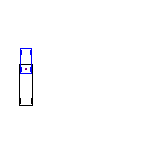 |
5thな「牽引車両」の屈曲後退の特徴を考察します。(センターアクスルなフル・トレーラーに対する屈曲後退の特徴は、有名な「ひらがさん」のWeb ページが詳しいので割愛します。)http://homepage3.nifty.com/garahi/Driving.html |
|
(1)トラクターとトレーラーが一直線に停止した状態から、据え切りハンドルで一定回転切り、前進す
るとします。当然、トラクターと
トレーラーは徐々に折れ曲がっていきます。折れ角が一定角度に達する前、つまり、トラクタとトレーラが徐々に折れてきている途
中の状態の時で、ハンドルをそのままの状態で後退するとどうなるでしょう。5thなら、元の一直線の状態まで戻る事ができます。
(2)ところが、そのまま前進し続けたとすると、トラクタとトレーラは一定の角度を維持しながら旋回
するよ
うになります。この状態になった時以降に、後退するとどうなるでしょう。(連結器のあそびなどの影響を無視すると、)その角度を維持したまま旋回し続ける
のが
判ります。決して元の直線状態に戻りません。逆に、更に折れ込んだりもしません。後退でも、大体の同一半径で旋回を続けます。
以上の2点は、私自身がセンターアクスルなフルトレーラーで体験した記憶とは異なります。センターアクスルなフルトレーラーでは、(1)の場合でも後退 すると更に折れ曲がってしまって元の一直線の状態には戻りませんし、(2)の場合でも前進のみの場合なら「一定の角度を維持して旋回をする様になります」 が、その状態から後退を開始するとトレーラーは更に折れ込んでいってしまいます。センターアクスルなフルトレーラーに於いて、一定角度を保って後退する為 には「トラクターに対するトレーラーの角度が左右45度の場合」のみだった様な気がします。 5thなら、30度でも、40度でも、85度でもトラクターのハンドルの切れ角次第で、一定角度を維持して屈曲バックを続ける事が可能です。 では、後退で一定の角度を保ち旋回している状態から直線状態に戻すためにはどうすればいいでしょう。
トラクターをトレーラーに対して一直線に「伸ばす」為には、きっかけハンドルとして後退中にハンドルを切っている方
向にさらに深く切る(これを「伸ばしハンドル」と呼びます)のです。すると、トラクタの回転半径が今までより小さくなり、トレーラと
の折れ角が徐々に小さくなって、やがて直線状態になります。このときハンドルを元に戻せば、完全に元の直線状態に戻ります。問題は、ハンドルを切る深さと
タイミングです。直線状態に戻る場所を計算してやらなければなりません。この部分には、勘と経験とセンスが必要になります。(残念ながら、私には全て在り
ませんが・・・)
以上の点が、フルトレーラーに対してセミトレーラーである5thの方が後退のコントロールが容易であると云える事です。「牽引車両」の屈曲後退に於い て、 意図的に「伸ばす」「折る」とのコントロールを加えない限り(路面の状況や遊びの範囲内で)一定の折れ角で同じ軌跡を辿るのです。勿論、(1)の様に一定 角度まで持ち込まない限り自然に一直線に戻ってしまいますが、屈曲後退から、やや「伸ばす」、やや「折る」と云う場合もハンドルの舵角にリニアに反応しま す。センターアクスルなフルトレーラー、で屈曲バックから「伸ばし」に移る時の様な大きな「伸ばしハンドル」の舵角は不要です。センターアクスル式フルト レーラーから、5thに乗り換えて最初に驚いたのは当にこの部分です。センターアクスル式フルトレーラーでは、大きな舵角の「きっかけハンドル」が必要 だったのですが、5thでは必要ではありません。但し、前述した様にトレーラーの操舵輪はトラクターの車体ですので、車体が必要とする角度に至る迄の「構 造的な動作遅れ」が在るので、それを待ち切れずについつい大きな舵角を与えてギクシャクと屈曲バックをしてしまうのは・・・私の事です。 |
|
では、応用編として、一定角度を維持している状態から折れ角を浅くしたり、深くしたりするにはどうすればいいでしょう。
右に折れている場合
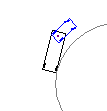 |
折れ角を浅くする
ハンドルを切っている側に、更に深く切ります。
トラクタとトレーラは伸びていきます。必要な角度になったらハンドルを戻します。すると、旋回半径が大きくなります。伸ばしハンドルで直線になる途中で止
めた状態です。(右に折れている場合、右に切る) |
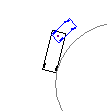 |
折れ角を深くする
ハンドルを切っている方と反対に切ります。
(右に折れている場合、左に切る) トラクタとトレーラは折れていきます。必要な角度になったらハンドルを戻します。すると、旋回半径が
小さくなります。
|
|
我が家の牽引車は左ハンドルなので、左バックで説明します。右ハンドルな方は、やはり右バックが有利です。普段か
ら、屈曲バックを行う際は左バックで行う事にしています。尚、左バックだと、左側通行の日本では、バックする場所を運転席側(左側)で見ながら通り過ぎ
て、対向車線側にトラクターの頭を振っても安心してバック出来ます。教習場や検定コースでは右バックでは右側に寄せた状態で屈曲バック(車庫入れ)が出来
ますが、実際の公道上では右バックに都合の良い位置でのバックは出来ません。交差点での右折の際など左ハンドルで不便を感じる事もありますが、殊バックに
関しては道路事情に合った左バックが楽に出来る左ハンドル車のトラクターは良いと私は思っています。(道を間違える事の多い私は、公道上で何度も方向転換
を実践しましたが、以前の右ハンドルの牽引車では妻子を総動員して後方監視と道路上の交通整理をして貰わないと方向転換は出来ませんでした。)
我が家の駐車環
境(自宅車庫)への車庫入れ
我が家の駐車環境とは、幅員3.8mの前面道路から、直角に幅員5m・全長14.5mの車庫への車庫入れです。トラクターの全幅は2. 3m、トレーラーの全幅は約2.5m、連結全長は通常時13mですが、自動スライドヒッチが作動する為、屈曲後退では全長が60cm伸びます。下記のス タート位置を例にすると、左側に50cmの余地を空けて停止するとトラクターの右側には、僅かに1mの余地しかありません。これは正直な話、岡山県の運転 免許試験センターのコースより不利な状況です。
我が家の駐車環境とは、幅員3.8mの前面道路から、直角に幅員5m・全長14.5mの車庫への車庫入れです。トラクターの全幅は2. 3m、トレーラーの全幅は約2.5m、連結全長は通常時13mですが、自動スライドヒッチが作動する為、屈曲後退では全長が60cm伸びます。下記のス タート位置を例にすると、左側に50cmの余地を空けて停止するとトラクターの右側には、僅かに1mの余地しかありません。これは正直な話、岡山県の運転 免許試験センターのコースより不利な状況です。
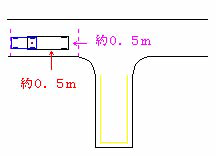 |
<スタート位置> ●車庫の前を横切り、横は縁石から50cm程離して、直線状態で停止します。 同じく、トレーラ後端がカーブの端から50cm以上離れるように止めます。 本来は、もう少し前に出した方が折れ角を大きくせずに有利なのですが、我が 家の駐車環境では、これ以上前に進むと隣家の塀にぶつかります。 |
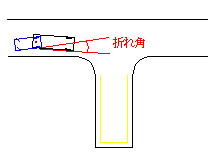 |
●「きっかけハンドル」として右に1回転半切りながらバックします。ハンドル
の切れ角が大きいので一気にトレーラーが折れ始めます。車庫入れに、必要な 折れ角に達する迄の距離が短いので充分な折れ角が必要です。我が家限定での 目安は、トレーラーの左側の延長線が自宅の塀を辛うじてクリアする角度です。 |
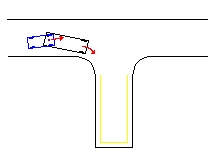 |
●必要な折れ角に達したら、ハンドルを直進状態に戻します。最初に充分に折れ 角を付けたので、これ以上トラクターを左に寄せないまま、後僅かに折れ角を 付けて、トレーラーの車輪がカーブの端の僅か前に達するのを待ちます。又、 道路に対してトラクターが平行に成るのが目安です。 この行程を入れないで、必要な折れ角へ一気に持ち込んで、「伸ばしハンドル」 で押し込もうとすると、先ずトラクター左前輪が脱輪(自宅の塀にぶつかる) してしまいます。我が家の様に狭い環境では止むを得ないテクニックですが、 実際に公道上で方向転換する際にも役に立ちます。 |
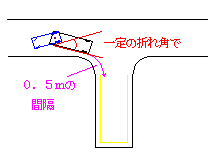 |
●ハンドル直進で押しながら、トレーラーが車庫に入るポイントを見切ります。
ここで据え切りでにハンドルを左に回し、一定の折れ角を維持する角度を探し ます。(探します・・・とは悠長に聞こえるカモしれませんが、速度を落とせ ばジックリと曲げと伸びの具合が見えますので、速度を落とします。)角度は 我が家の場合だと45度位です。これより浅いと右隣の隣家の塀に突き刺さる し、これより深いとトラクターが大きく脹らみすぎて、トラクターの右前輪が 脱輪します。(本当に土手から川に落ちます。)車庫の右側は隣家の塀なので 自宅の家側の余地を50cmと少なめにとりバックを続けます。バックモニタ ーで隣家の塀の根本が見えれば安心出来ます。 |
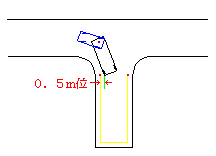 |
●45度の折れ角を保ちながら、そのままバックを続けます。我が家の場合は、
検定コースより幅は広いのですが、浄化槽等邪魔な物が在り、トレーラーの タイヤを正しく車乗部分(約3m幅)に載せなくてはなりません。(直角の 90度に対して半分の45度は、最もコンパクトな屈曲バックが可能な角度 です。後述するハブベアリングへの負荷は心配ですが、日頃からコンパクト に屈曲バック出来る癖を付けておかないと公道上での方向転換で困ります) |
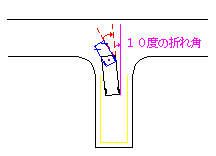 |
●トレーラー後部が浄化槽上の車乗部分に正しく載ったとバックカメラで確認後
トレーラーとトラクターを真っ直ぐ伸ばす準備を始めます。当然な事ですが、 車庫に対してトレーラーが真っ直ぐになった後では遅いです。又、前面道路の 幅員が狭いのでトラクターにだけ折れ角が残っている状態では、前に引っ張り 両車を真っ直ぐに直すだけの移動距離が足りません。目安として、車庫に対し 約10度の折れ角が残った状態で、一定の折れ角を維持していたハンドルを、 更に左に切って、トレーラーとトラクターを一直線にしながらバックします。 |
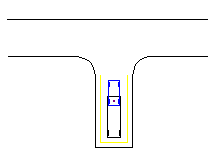 |
●トラクターとトレーラーが一直線になったら、ハンドルを直進状態に戻して、 直線バックの要領で更に押し込みます。 ●片側に寄っていたり、斜めに停まっていると、次回牽いて出動する時に私自身
が不便なので、一旦前に出してキチンと真ん中に収めます。検定では切り返し に当たるのでしょうが、そんな事は気にしません。又、キャンピングトレーラ ー全般に云える事ですが、ハブベアリング等が弱いので屈曲バックで車庫入れ を1発で決めて喜んでいると、トレーラータイヤの「捩れ」が残っていてハブ に無理な力を掛け続けてはイケナイと、必ず、一旦前に牽っぱり直線バックで 車庫入れをやり直してタイヤの捻れを取っておく事にしています。 |
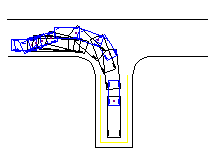 |
上記の成功事例では、左図の様な軌跡を通って車庫入れをしています。このコースならば、 我が家の駐車環境の様な狭い場所でも車庫入れが可能です。基本形として練習を重ねるしか 無いと思います。因みに、この軌跡は車庫から前進で出庫する際の軌跡とほぼ同じです。普 通の屈曲バックで入らないキャンプ場のサイトに切り返しを繰り返して無理矢理停めたのは 良いけれど、サイトからの出庫の際にも何度も何度も切り返しをしないと出られないって事 が・・・私個人的には多いです。 |
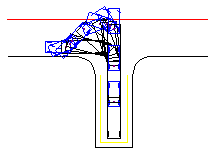 |
我が家は前面道路が狭いので、更に折れ角を付ける事は不可能です。ですが、トラクターが 大きく頭を振るだけの車庫前方のスペースが在る環境では(更に、スタート位置を充分に前に 取れない環境では)左図の様な軌跡も取ることが可能です。しかし、トレーラーが90度近く 折れているとトレーラーのタイヤは殆ど回転しませんから、既述の通りハブベアリングへの負 担は大きくなります。しかし、この方法なら「牽引車両」の全長分だけスタート位置が在れば 苦労はしても車庫入れを完了する事が出来ます。トラクターの軌跡を見てお分かりの通り、約 1/3周(120度)以上トラクターが旋回するので、ハンドル操作のタイミングは微妙です。 「牽引車両」は折れ曲がるので、その車両全長に対する回転半径は小さくなるのですが、ト ラクター単体の最小回転半径は牽引時でも非牽引時でも変わりません。折れ角を大きく取った 屈曲バックの場合もトラクターの最小回転半径の大小に全体の回転半径の大小が大きく影響を 及ぼします。 |
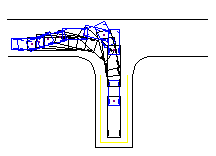 |
他の車庫入れの方法は、縁石のカーブに一定間隔で沿わないで折れ角を変えながら屈曲バッ クを継続するやり方です。(岡山県トラック協会の練習場の怖い教官のおじさんは、この方法 を唾を飛ばして伝授してくれました。「我々トレーラー運転手の荷先は一定では無いので、 どこに行ってもバックが出来ないと困るだろう?」と云われたのですが、私は軟弱にも趣味で しかトレーラーを動かさないので勘弁して欲しいと思ったのですけど・・・) この方法が良い点は、荷先の他の車両や建物に接触する可能性が最も低いからだそうです。 ですが、自宅への車庫入れでも、キャンプ場でのサイト入れでも、こんな軌跡を通ってバック している事が・・・案外多いようです。(但し、この方法と基本形が途中でゴッチャになる と、特に自宅前ではリカバーに困る自体になるので・・・要注意です) |
検定試験では、切り返しは5点ずつの減点で、3回以内に方向転換を完了しないと検定中止です。幸い、自分は切り返
しせずに方向転換をクリア出来たので良かったのですが・・・。技能検定では切り返しは恥ずべき行為カモ知れませんが、実際の公道上での屈曲バックでは、下
手くそなので毎度毎度御世話になっています。これもコツがあるようで、最初は自宅前でも検定中止(3回以上の切り返し)をしていましたが、最近では、ハブ
ベアリングへの負担を減らすと云う云い訳で、結構御世話になっています。
切り返しの簡単な考え方は、屈曲バックに於ける「基本ライン」上に戻すことです。しかし、切り返しの必要な状況下とは、短い距離で失敗した屈曲バックの
リカバーを行う訳ですが、トラクターの位置だけ基本ライン上に戻っても、トレーラーの位置や角度が違えば、その後のリカバリーでも対処出来ない場合もあり
ます。基本ラインに戻せない場合は、諦めて、スタート位置まで戻すべきです。
|
|
|
|
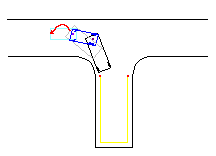 トレーラー左後部が車庫入り口に接触しそう。 |
●停止位置が前すぎ。 ●きっかけハンドルの切れ角が深すぎる。 ●折れ角が深い。 |
一旦、右にトラクターを前進させる事でトレーラー後部をカーブの角から離し、その上で、左 に戻して折れ角を調整する。 基本ライン上に戻す切り返し。 |
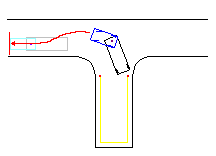 トレーラー右後部が車庫の壁に当たりそう。 |
●停止位置が後ろすぎ。 ●きっかけハンドルの切れ角が浅い。 ●折れ角が浅い。 |
車庫前方スペースが無いので、右前方への切り返しは不可能。 基本ライン上に戻す事は困難。 最初の停止位置に戻った方が無難。但し、出来る限り、トラクターとトレーラーを一直線に戻す事。
|
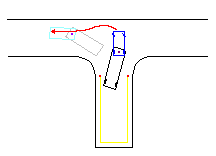 トレーラーは入り口に浅く入ったが、左後端が当たりそう。 |
●折れ角が深い。 ●伸ばしが遅い。 |
車庫前方スペースがないので、車庫前方への切り返しは不可能。 左に戻り、トレーラー後部をカーブの縁石から充分に離し、折れ角を調整して基本ラインに載せる。 ★(他の方法) この位置なら、逆に、右に頭を振って前進し、浅い右バックに移行する。 |
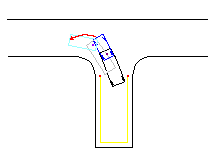 トレーラー後部は入り口に浅く入ったが右後端が当たりそう。 |
●折れ角が浅い。 ●伸ばしが早い。 |
トレーラ後部が基本ラインから離れているので、左に戻り、折れ角を調整し直して、基本ラインに載せる。 ★(他の方法) T字の突き当たりまで斜めのまままっすぐ前進してトレーラ後部をできるだけ真ん中に持っていき、きっかけハンドル・折れ角維持・伸ばしで直線バックに持っ て いっても可。 |
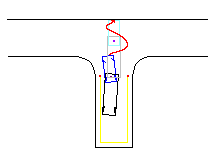 トレーラー後部は車庫に深く入ったが左後端が当たりそう。 |
●伸ばしが少し遅い。 |
前方に余裕があるので、基本ライン上に戻す必要は無い。 トラクターを、一旦右へ振ってトレーラ後端をできるだけ車庫幅の真ん中へ誘導し、トラクターとトレーラーを可能な限り直線にし、直線バックの要領で押し 込む。 |
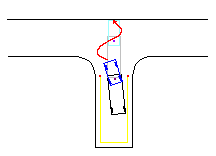 トレーラ後部は車庫に深く入ったが右後端が当たりそう。 |
●伸ばしが少し早い。 |
前方に余裕があるので、基本ライン上に戻す必要は無い。 トラクターを、一旦左へ振ってトレーラ後端をできるだけ車庫幅の真ん中へ誘導し、トラクターとトレーラーを可能な限り直線にし、直線バックの要領で押し 込む。 |
基本ライン上に戻す事には拘らず、やり直し易い位置に切り返すべきです。
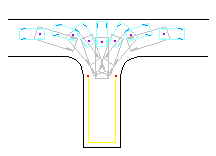 |
基本のスタート位置が最も簡単な車庫入れのスタート位置ではありません。失敗して行き詰まった状態からト レーラーをドコに牽っぱり出せば良いかを考えます。トレーラを押し込みやすい「トラクタとトレーラの状態・位置」は概ね決まっています。 それは、左図のように車庫の入り口を中心とした扇形の放射線上を 考えればいいのです。狭い場所での切り返しでは、やり直しスタート位置は、できるだけT字の上辺近くま で頭をもっていき、距離を稼いだ方が修正が効きます。トラクタを少しだけ前に動かしてもトレーラの状態はあまり変わりません。 当然、やり直した時のライン取りは基本ラインから外れたライン取りになりますが、要領は基本ラインの
時と同じです。
|