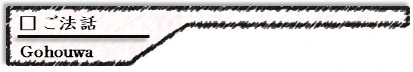講師からのコメント
往生ほどの一大事
凡夫のはからふべきことにあらず
ひとすじに如来にまかせ奉るべし
覚如上人『執持鈔』
核の時代80年にあたって
すべてのいのちの道
なもあみだぶつ
合掌
身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も
ほねをくだきても謝すべし
(恩徳讃)
本日は、白骨の御文章についてお話し致します。 御文章とは、蓮如上人が親鸞聖人の教えを分かり易くお書きになったお手紙です。 昔は「おふみ」と呼ばれていましたが、西本願寺では「御文章」というようになりました。 また、読む文章ではなく、聞く文章として書かれ、仏事で拝します。
白骨の御文章がどのような理由で書かれたのか厳密には不明となっていますが、ある一説を紹介します。 山科の土地を寄進した海老名という方の娘が亡くなり、母親がその死をあまりに悲しむため、 父親が蓮如上人に手紙を依頼したのが由来と言われています。しかし、この御文章には宛先がありません。 そのため、無常を伝えられた法語ではないかと思うわけであります。
この御文章は滑らかな文章になっており、「それ〜しげしといへり」までは、 存覚上人の『存覚法語』から流用されています。 さらに、『存覚法語』は後鳥羽上皇の『無常講式』を流用した文章となっています。 「この世の始中終」とは、一生の少年(始)、壮年(中)、老年(終)のことです。 三回「されば」という言葉が使われています。 一回目の「されば」は、前文の「まぼろしのごとくなる一期(人の一生は幻のようなもの)」を受けて「一生過ぎやすし(一生はあっという間)」と言っておられます。 二回目の「されば」は、、「今日ともしらず、明日ともしらず」を受けて後文の朝夕を待たずとなります。 「夜半の煙」とは、昔は火葬を夜中を通して行っていたので、このような表現となっています。 よく意味を間違えてしまうのが、「あわれといもなかなかおろかなり」という文です。 ここの「おろか」は「愚か」ではなく、「疎(おろそ)か」という意味で、「何度言っても言い表せない」となります。最後の「されば」は全体の結びとなっています。そして「後生の一大事」という言葉は蓮如上人の造語と言われ、「死んだ後の行く先を定めることが最も大切なこと」、それは「阿弥陀様の極楽浄土ですよ」と言われています。
白骨の御文章は通夜や葬儀の時に拝読しますが、本日はこの無常観を味う機会にして頂ければと思います。
| 南無阿弥陀仏 |

| 聴聞の心得 |
|
一、このたびのこのご縁は初事と思うべし |