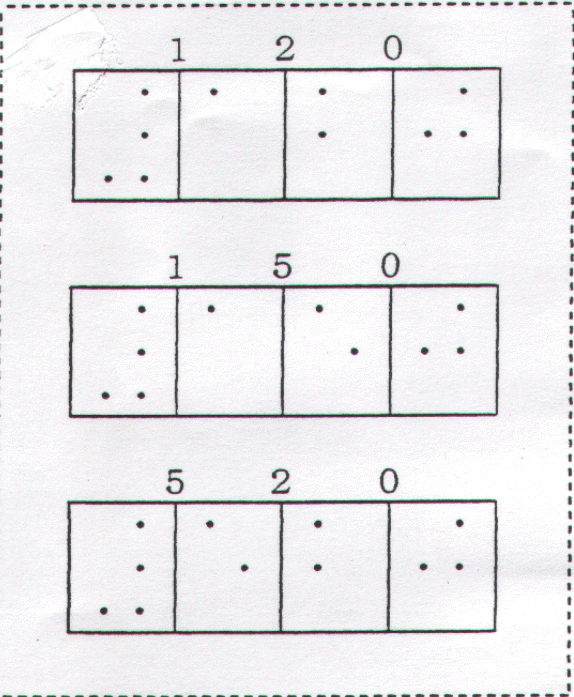 |
(発問1) 左の手がかりを見て、気づいた ことを言って下さい。 |
|||||
| 子ども達は、 ・最初と最後は全部同じ。 ・最後のはたぶん「0」だと思う。 ・最初のは百の位だと思う。 ・「あ」の点は「1」だと思う。 ・「い」の点は「2」だと思う。 ・じゃあもう一つのは「5」だ。 といったような反応を示した。 そこで、最初のは「数符」と言い、これから数字が始まるという記号であることを説明した。 |
||||||
(C)Two-Way/トスランド/小学校/算数/第4学年〜第6学年/
|
|
広島県福山市立水呑小学校 教諭 粟村啓史
九月、第4学年の子ども達は50音程度の点字を学習した。
今回は、算数科の学習の中において、総合的な学習との関連を図りながら学習を進めていくことを考えるとき、どのような学習素材やどのような学習展開が考えられるか、ということを念頭に置いて、点字に焦点を当て、点字を学習素材としたときの算数の学習を考えてみた。以下、その実践を示す。
この「点字と算数」の実践は、3時間をワンセットとして組んだ。
|
|
|
という具合である。
第1時、まず宝箱風の大きめの箱を用意する。その箱の中には第二、第三の箱があり、箱を開けるために挑戦する算数の問題が同封されている、という設定である。 第1時、子ども達の前に宝箱を示す。箱の前面には点字の数字でキーナンバーが書かれている。その部分を見せると、子ども達は「点字だ、点字だ。」と言った。50音を学習したときの知識で点字を読もうとするが、数字が示してあるのでうまく読めない。この時点では、子ども達はまだこれが点字の数字なのだとは気づいていなかったのだ。50音で読んでも意味が通じないのである。そこで、これは点字の数字であることを告げ、今日は点字の数字を学習する旨を告げた。
手がかりとなる次の3枚を提示して、「何か気がつくことはないか。」と問うた。
|
||||||||
また、子ども達からは、「上部の四点しか使われていない」という意見が出なかったので、
(説明1) 点字の数字は上部の四点しか使われません。 |
と、説明した。そして、これら3つの手がかりだけではまだまだよく分からないことを確認し、
(発問2) 四点を使って、どのような点の打ち方が考えられますか。考えられる限り、全 部書いてみましょう。 |
と発問した。
数名の子ども達は書き始めようとしていたが、手こずりながら手が止まっている子もいた。バラバラに考えている ようなので、作業を止めさせ、
(発問3) 落ちやダブりがないように上手にするには、どのようにすればいいですか。 |
と問うた。「順番に」「順序よく」などの反応があった。どのように順序よくなのかさらに問うと、
・点が一つの時、点が二つの時、点が三つの時、点が四つの時、というふうに分けて考えたらいい。
と反応した子がいた。そして、その通り「順序よく」分けて考えるよう指示してプリント作業させた。その後、
・点が一つの時・・・4通り
・点が二つの時・・・6通り
・点が三つの時・・・4通り
・点が四つの時・・・1通り
の15通りであることを確認し、一つ一つカード化して黒板に貼らせた。
その後、上記と同じような手がかり用のプリント(算用数字と点字の数字とを併記し、10種の3桁の数が書いてある紙)を配り、算用数字と点字の数字とを対応させながら、一つ一つの数字を確認していった。
そして、点字の数字は点字50音の「ア行」と「ラ行」に相当すること、数字に使われていない点字は「拗音符」「濁音符」「拗濁音符」「長音符」「促音符」に使われていることを説明した。ちなみに、「1234567890」は「アイウルラエレリオロ」に相当する。
この日はここでストップ。第1時の終了である。子ども達は、キーナンバーが分かり宝の箱を開けるのだろうと期待していたようだが、それは第2時のスタートで扱うので、この日はここでストップなのである。その後、ノートに感想を書かせ終了した。
子ども達からは、今日の授業は楽しかった、点字の数字が読めるようになってうれしい、点字に興味を持った、もっと勉強したいと思った、今日箱を開けなかったのでがっかりした、などの感想が多くあった。
・表紙へリンク ・第2時へリンク ・第3時へリンク
TOSSランドへ メールはこちらから
(C)TOSS Awamura
Hirofumi All right reserved.